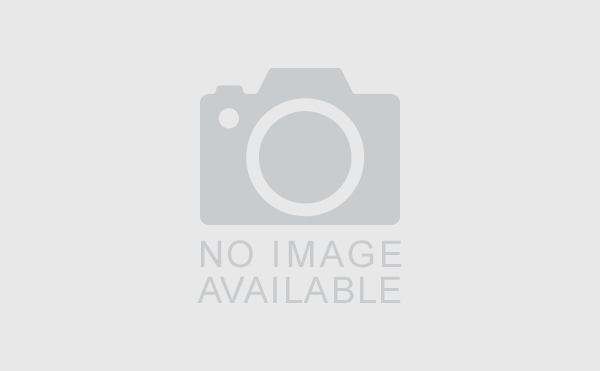2025年2月2日 主日礼拝「神の召命」
礼拝式順序
賛 美 プレイズ「忘れないで」
新聖歌38「わが目を開きて」
前奏(黙祷)
招 詞 詩篇95篇6〜8節
讃 美 讃美歌5「こよなくかしこし」
罪の告白・赦しの宣言
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 讃美歌194「さかえにみちたる」
聖書朗読 コリント人への手紙第一1章26〜31節
説 教 「神の召命」
讃 美 讃美歌249「われつみびとの」
聖餐式 信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
讃 美 讃美歌206「主のきよきつくえより」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 ヨハネの福音書15章16a節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
コリント人への手紙第一1章26〜31節
説教題
「神の召命」
今週の聖句
あなたがたがわたしを選んだのではなく、わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命しました。
ヨハネの福音書15章16a節
説教「神の召命」
コリント人への手紙第一1章26〜31節
「あなたがたがわたしを選んだのではなく、わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命しました」(ヨハ1516)。このイエス様のおことばに、これまでどれだけ多くの人が慰められてきたことでしょうか。もちろん、私もその中の1人です。このような罪人を、このような弱い者を、主が選んでくださり、招いてくださり、救ってくださった。私は自分から、自分の意志で救いを求めて教会に来たのかもしれない。しかしそれよりも前に、主のあわれみと招きがあったとは。そのことを知った時の驚きと感動を今でも覚えています。皆さんもそうなのではないでしょうか。
そしてこれに続くおことばも私たちのお気に入りなのではないでしょうか。「それは、あなたがたが行って実を結び、その実が残るようになるため、また、あなたがたがわたしの名によって父に求めるものをすべて、父が与えてくださるようになるためです」。父なる神さまは、私たちが望むものをすべて与えてくださり、私たちを喜ばせ、私たちを繁栄させてくださる。父なる神さまは、私を愛してくださっているので、私が祈るならば私の望みをすべて叶えてくださる、望みの自動販売機のようなお方。望みのボタンを押せば望みのものが無条件で与えられるよ。イエス様はそのようなことを言われたのでしょうか。もちろん、私たちに必要とあれば、無条件に(その意味は、行いによらず恵みによって)与えてくださるでしょう。しかしイエス様はここで「あなた“がた”は“行き”なさい」と言われるのです。私たちはコリント人への手紙の前に、マタイの福音書を学んで来ました。その最後に記されているイエス様のおことばを思い起こすのではないでしょうか。ここに私たち教会に対する一貫した主の御心があり、召命があり、命令があるのです。すると、私たちが結ぶ実とは何か。残す実とは何か。主の御名によって神に求めるものは何かが分かってくるのではないでしょうか。
そしてさらに、この後すぐにイエス様が言われたことも忘れてはなりません。切り離してはなりません。「あなた“がた”が互いに愛し合うこと、わたしはこれを、あなた“がた”に命じます」(ヨハ1517)。愛とは何か。何度も教えられて来ました。愛とは「好き、好き、大好き」だけではありません。「大切」です。神が私たちを愛したように、神が私たちを本当に大切にしてくださったように、私たちも互いに愛し合う、互いに大切にし合うのです。
教会は神の召しを受けた者たちの集まりです。神はこの世に教会を置き、教会を通して、神の力と知恵の福音をこの世に証される。ですから教会はこの世に存在するのは当たり前。しかし教会の中にこの世が存在していてはならないのです。この時のコリントの教会の状況については、前々回、前回と見てきた通りです。コリントの教会には分争があった。もともとは自分のお気に入りの説教者を立てて、分かれて争っていた。それはやはりグループ間だけの争いには留まらなかったでしょう。教会の中は争いや対立でバラバラ。すったもんだ。この世とまったく変わらない争いがあったのです。もうそれは世の悲惨な戦争と同じようなものです。そこにイエス・キリストの十字架のメッセージに対する不信仰と誤解が生じてきてしまっていたのです。皆が立ち返るべきはイエス・キリストの十字架のメッセージ。なぜなら、イエス・キリストの十字架のメッセーによって皆が神に呼び集められた、それがキリストの教会なのですから。
パウロは自分が伝える福音が、人々の期待とは様々な面で異なることを知っていました。人々は自分の期待どおりに福音を聞き、期待どおりに受け取ってしまっていたのかもしれない。そこでパウロはコリントの聖徒の弱くて足りない面を説明しながら、神の召命の特徴とその意味を教えて行きます。
コリントの教会の人たちは、もちろんコリントの町、その町の文化の中から救われ、そして召された人たちです。元々ギリシア人の町で、当時も世界中から様々な人たちが移住してきていたとは言え、やはりギリシア人が多く住み、その色彩が色濃く残る町でした。その町の文化というのは、自己顕示と自己アピールの文化でした。自分自身を目立たせることで、周囲から注目や褒められたいという欲求が当たり前のようにあり、またそれを良しとする町。コリントの教会の人たちは、それをいかに上手にするかが知恵の基準となっていました。そこで分派が生まれ、教会内でリーダーたちの名を借りて自らを高めようとしていました。他のグループを低めようとしていました。互いに愛し合うどころではなかった。パウロはそのようなコリントの教会の人たちに、「誇る者は主を誇れ」と教えます。
自分たちの召しのことを考えてみなさい
1章26節 兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。
パウロは「自分たちの召しのことを考えてみなさい」と言います。
この「考えてみなさい」というギリシア語は「見つめなさい。見よ」というものです。神は聖書の中で何度も「見よ」と言われますね。そして「考えてみなさい、見つめなさい、見よ」の中には「何かに驚嘆する、感動する、驚く」というニュアンスが含まれています。私たちもそれぞれの神の召し、神がこの私を選ばれたということをしっかりと見つめるならば、そこに大きな感動、驚きが起こってくるのではないでしょうか。
「知者」とは、学識のある、教養のある、教育水準が高い人たちのことを指しています。「力あるもの」とは、社会的影響力を持つ人たちのこと。「身分の高いもの」とは、上流層の人、高貴な生まれの人のことを指しています。
最近の研究によると、コリントの教会には3つの種類の人たちがいたと推定されます。1つはごく少数の「エリート層」。高い地位のある者の家に生まれ、裕福。社会的にも政治的にも影響力を持っていた人。コリント教会のメンバーの5%程度でした。1つは「中間階層」。彼らは奴隷ではない自由人で、コリント教会のメンバーの20%ほどでした。実はこのグループの中に野望を持つ競争心の強い者たちがいて、コリント教会の中に分裂を生じさせたと考えられています。そしてもう1つは「多くの貧しい人」。コリント教会のメンバーの70%ほどを締めていました。ほとんどがこの「貧しい人」でした。コリントの教会はまるでこの世の縮図のようです。
コリントの教会のメンバーのほとんどは、ギリシア文化の教育(修辞学など)を受けていない貧しい者たちで、彼らは世では弱く、差別されていたようです。彼らは当然口では負けてしまうでしょうし、発言さえ許されていなかった部分もありました。コリントの教会のメンバー構成は、確かにこの世の縮図のようではありましたが、やはりこの世の基準をそのまま教会の中に持ち込んではならないのです。教会の基準はあくまでも神の基準によらなければならない。
貧しい彼らこそ深く考え、神と親しく交わる者たちであったでしょう。神に依り頼む者たちであったでしょう。そして彼らは、同じコリント人の手紙の中の4章12節によると、自分たちの手で働いた者たちでした。それでも貧しく、人々に中傷されても、それでも神を信じ、中傷する相手に優しいことばをかけていたようです。社会の中では迫害されては神に依り頼んで耐え忍んでいたようです。
そして興味深いことに、パウロは明らかにエリート層の人だったのに、この「貧しい人」のグループに自分を置くのです。自らの罪を知り告白し、イエス・キリストの十字架のゆえにその罪を赦された者の謙遜、へりくだりの姿です。私たちはどのグループに自分を置くでしょうか。
このようにコリントの教会の人たちの多くは、社会的に影響力のある立場にはなく、ほとんどがごく普通の一般市民でした。知性や力、権力などが特に優れているわけではありませんでした。神は人間的な基準とは関係なく救いを与えてくださったことがこのことからも分かります。どんな身分や学歴であれ、救いは福音を受け入れてイエス・キリストを信じること以外の方法では得られないのです。皆、神に救いを求め、イエス・キリストを信じ、そしてこんな私さえも救いへと招いてくださった神の愛、あわれみ、招きに感動し、そして救われた者たちでした。はずでした。それなのに分争があったとは。貧しい人たち、真に神に依り頼む者たちを巻き込んで、ごく少数のエリート層の人をリーダーとして担ぎ上げて、リーダーたちの名を借りて自らを高め、分派を作り、権力争いに巻き込む一部の者たち。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派。これらは偶像礼拝と並ぶ重大な罪に数えられています。その罪が教会の一部の人の中にあった。たとえ一部であったとしても、教会はキリストの「ひとつからだ」ですから、全体に悪影響を及ぼしてしまうのです。そしてそれは、神の国を相続することを出来なくしてしまう。滅びへと向かってしまうという、恐ろしい結果になってしまうのです。
ですからパウロは強く勧めるのです。「自分たちの召しのことを考えてみなさい」と。自分が救われた時のことをよく見つめてみなさいと。このような私が神に選ばれた。このような私が救われた。このような私が神に召された。あなたの救いも、あの人の救いも。あなたの召しも、あの人の召しも、間違いではない。「神の愚かさは人よりも賢い」のだと。そして「神の賜物と召命は、決して取り消されることがない」(ロマ1129)のだと。そこから感動と驚きをもう一度思い起こすのだと勧めるのです。
神の選択
1章27節 しかし神は、知恵ある者を恥じ入らせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じ入らせるために、この世の弱い者を選ばれました。
「神の愛とあわれみによって召され、救われたあなたは、自分自身を知恵ある者とするか、愚かな者とするか。強い者とするか、弱い者とするか」。この問いかけが今日の箇所のベースにあると言って良いでしょう。とても重要な問いかけです。
1章28節 有るものを無いものとするために、この世の取るに足りない者や見下されている者、すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです。
ここの「選び」というギリシア語は、「〜から外に」という前置詞と、「言う」を意味する動詞からなる合成語です。難しいですが、簡単に言うならば、神の「選び」というのは、神の口から出された宣言によるもの。つまり全面的に一方的な神の主権によるのだということです。
「神の愛とあわれみによって召され、救われたあなたは、自分自身を知恵ある者とするか、愚かな者とするか。強い者とするか、弱い者とするか」。皆さんは先ほどのこの問いかけの答えを出されたでしょうか。そしてその答えをもって、神の主権による選びに対して、どのような思いを抱かれるでしょう。パウロがコリントの教会の人たちにこのようなことを言うのは、「知者」「力ある者」「身分の高い者」「見下されている者」「無に等しい者」、皆を辱めて批判するためではなく、神が皆を選ばれた理由をもう一度思い返して、皆が慰められる、皆が励まされる、そして皆が真の悔い改めへと導かれるためでしょう。
そして神の選びとは。
神は、世では見下されている者を選ばれた。年老いたモーセが出エジプトの指導者とされました。エッサイの末の子ダビデが王となりました。教育を受けていなかった漁師たちが弟子として召されました。年をとっているとか、若いとか、力がないとか、多くを学ばなかったとか、持っているものが何も無いからと落ち込む必要はありません。逆に責められるものでもありません。神はただへりくだってご自身に依り頼む者を、ご自身の栄光を現すために用いられるのだからです。
神の御前で誇る
1章29節 肉なる者がだれも神の御前で誇ることがないようにするためです。
「肉なる者」。人はだれも、律法を行う事によっては神の前に義と認められないのです。律法と通して生じるのは罪の意識だけでしょう。善を行いたくても行えない。心に浮かぶ考えは悪いことばかり。コリントの教会の人たちばかりでなく、私たちは誰一人として、神の御前で誇ることなどできない者たちです。「自分の手で、自分の力で、自分の知恵で、自分を救った」と言って、誇ることなどできない者たちです。人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、コリントの教会の人たちも、そして私たちもイエス・キリストを信じました。ですからパウロは、コリントの聖徒に自己満足や自己宣伝のために誇る根拠などないということを明らかにしながら、自分の方が優れていると互いに争っていたコリントの聖徒を厳しく注意するのです。
主を誇れ
1章30節 しかし、あなたがたは神によってキリスト・イエスのうちにあります。キリストは、私たちにとって神からの知恵、すなわち、義と聖と贖いになられました。
「しかし、あなたがたは神によって」。ここを直訳すると「しかし、あなたがたは“この”神によって」となります。「この神によって」。どの神ですか。どのような神によってですか。ここでも手紙の読者は「自分たちの召しのことを考え」ることが求められているのでしょう。考えなさい。見つめなさい。そこから何かに驚嘆し、感動し、驚きなさいと。
どの神ですか。聖なる神、唯一の真の神、全知全能なる神。
どのような神ですか。さばきの神ですか。愛と憐れみ、真実の神でしょう。
そしてこの神は、罪人を救うためにイエス・キリストを十字架につけられました。
あなたがた(私たち)はこの神によってキリスト・イエスのうちにあります。あなたがた(私たち)が今、キリスト・イエスのうちにあるのは、“この”神によるのです。「この神によらずして、ここにあらず」なのです。
ところで、「キリスト・イエスのうちにある」と聞いて、思い起こす賛美があります。「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者。古きは過ぎ去り、すべてが新しい。主のうちにあるなら、すべてが新しい♪」という賛美です。元のみことばは「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべでが新しくなりました」(Ⅱコリ517)。この「見よ」も「考えなさい」と同じです。見つめて、驚き、感動するのです。
キリスト・イエスのうちにあり、その人はどのように新しく造りかえられるのでしょうか。
キリストは十字架により、神と私たちの間の仲裁者となられ、キリスト・イエスのうちに私たちは義と聖と贖いを得ました。
「義となる」というのは、神の御前に正しい者として立つことができるようになるということです。罪人であるすべての人間は、本来は神の御前に立つことなど許されないのですが、イエス・キリストを信じる者は、その信仰によって神の御前に立つことが許されるのです。罪ゆえに神との間に厚い壁が立てられ、神を知ることも、神と交わることもできなくなってしまった人間が、イエス・キリストにあるなら、何の隔たりも無く、神を知り、神と親しく交わることができるようになる。神に敵対するのではなく、神を心から喜ぶことができるようになる。死に向かって歩むのではなく、永遠のいのちに向かって歩むことができる。これこそが本当の救いです。
「聖となる」とは、神のものとして取り分けられるということです。罪赦され、しかしなおも罪が残るこの身ではあるけれども、イエス・キリストのゆえに神のものとして、また神に用いられる者としてこの世から取り分けられている。何度も申し上げておりますが、100万円のお皿でも犬のポチのために使えばそれまでですが、100均のお皿であっても、王のために用いるならばそれは本当に価値あるお皿になるのです。
「贖いとなる」とは、イエス・キリストが十字架で流された血の代価によって、罪の奴隷状態から解放され、神の子とされることです。「神の子」についてお話ししたことを覚えておられますか。神の子とされるというのは、養子にされるということでした。養子について、歴史的背景として、紀元1世紀のローマ世界において養子は、義父によって慎重に選ばれ、その名を引き継ぎ、財産を相続する者でした。養子は実子の身分に少しも劣らず、養父の愛情を十分に受け、養父の人格を反映して行く者でした。つまり神の子とされるというのは、神によって慎重に選ばれた者が、神の国を相続する者とされること。神の子とされた者は、神の御子イエス・キリストの身分に少しも劣らず、父なる神の愛情を十分に受け、注がれるその愛によって神の人格を反映して行く、注がれるその愛によってイエス・キリストの御姿に似た者とされて行く。
罪人である人間が、義とされることも、聖となることも、贖われることも、すべて神の一方的な恵みによるのです。神の選びによるのです。神の召きによるのです。そのために、神の御前で誇ることができる者は一人もいないのです。結局パウロは、自分を誇り、自分を高めようと教会の中で争っている者たちに対して、主の御心、主のみことば、主のご命令を言っているのでしょう。「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」(ヨハ1512)。「へりくだって、互いに尊敬し合い、自分よりも優れている者と思いなさい」(ピリ23)。それは何のためでしょうか。教会がそのように生きることによって、この世で神の栄光を現し、イエス・キリストの十字架のメッセージを宣べ伝え、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ。すべての下が「イエス・キリストは主です」と告白して、父なる神に栄光を帰するためです。
1章31節 「誇る者は主を誇れ」と書いてあるとおりになるためです。
「この神」はこう言われます。「知恵ある者は自分の知恵を誇るな。力ある者は自分の力を誇るな。富ある者は自分の富を誇るな」(エレ923)。「この神」はこう言われます。「誇る者は、ただ、これを誇れ。悟りを得て、わたしを知っていることを」(エレ924)。
神の知恵ではなく、自分自身を目立たせることで周囲から注目や褒められたいという欲求と、自己アピールの文化が広まり、いかにそれを上手にするかが知恵の基準となってしまっていたコリントの聖徒たちに、互いに争いコリントの教会に分裂を生じさせる聖徒に、「あのパウロ」が、愛をもって心から勧めるのです。「兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって、あなたがたにお願いします」と懇願するのです。「どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください」(Ⅰコリ110)と。「誇る者は主を誇りましょう」。自分自身を推薦する人ではなく、自分自身を賞賛して確固としたものにするのではなく、「主に推薦される人こそ本物ですよ」(Ⅱコリ1017−18)と励ますのです。
教会は神の召しを受けた者たちの集まりです。神はこの世に教会を置き、教会を通して、神の力と知恵の福音をこの世に証されるのです。ですから教会はこの世に存在するのは当たり前。しかし教会の中にこの世が存在していてはならないのです。この時のコリントの教会のように、誰が影響力があるかとか、地位や学歴、出身で人をさばくようなことがあってはなりません。主が問われるのは、ご自身に対する信仰です。神の御前ではすべての人が罪人であり、神の恵みによる福音を信じることによってでしか救われない。そして教会はそのようにして救われた者たちの集まりであるということをもう一度考え、見つめ、そこから驚きと感動をいただき、感謝と神への愛をもって、神と教会に仕え、神に用いられる者となり、この世で福音を伝えてまいりましょう。
この後、私たちは聖餐式に招かれています。この招きにあっても、今日のみことばを見つめつつ、聖餐の恵みに与りましょう。そしてイエス・キリストの十字架を覚え、この十字架の福音のもとに、互いの絆を確かめ合い、そして心ひとつにしてまいりましょう。