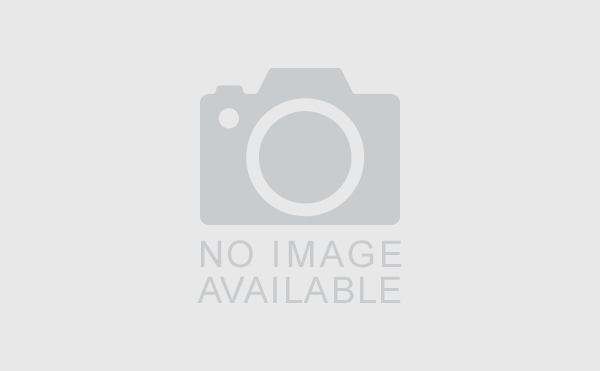2025年4月27日 主日礼拝「私たちは祝福を受け継ぐために召された」
賛 美 新聖歌257「キリストは生きておられる」
新聖歌254「こころにあるこの安きを」
前奏(黙祷)
招 詞 詩篇119篇33〜40節
讃 美 讃美歌162「あまつみつかいよ」
罪の告白・赦しの宣言
信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 讃美歌365「わが主イエスよ」
聖書朗読 コリント人への手紙第一7章1〜16節
説 教 「私たちは祝福を受け継ぐために召された」
讃 美 讃美歌520「しずけき河のきしべを」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 コリント人への手紙第一7章15b節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
コリント人への手紙第一7章1〜16節
説教題
「私たちは祝福を受け継ぐために召された」
今週の聖句
神は、平和を得させようとして、あなたがたを召されたのです。
コリント人への手紙第一7章15b節
説教「私たちは祝福を受け継ぐために召された」
コリント人への手紙第一7章1〜16節
- パウロは、今は終わりの時であり、終末の時にしっかり備えることが基本だと教えています。
- 性や結婚、その他の難しい問題に対する答えを求める時に決め手になるのは何でしょうか。
- 「神は、平和を得させようとして、あなたがたを召されたのです」の意味を考えましょう。
1、さて、「男が女に触れないのは良いことだ」と、あなたがたが書いてきたことについてですが、
2、淫らな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。
3、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。
4、妻は自分のからだについて権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように、夫も自分のからだについて権利を持ってはおらず、それは妻のものです。
5、互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのならかまいません。これは、あなたがたの自制力の無さに乗じて、サタンがあなたがたを誘惑しないようにするためです。
6、以上は譲歩として言っているのであって、命令ではありません。
7、私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、一人ひとり神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。
8、結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるなら、それが良いのです。
9、しかし、自制することができないなら、結婚しなさい。欲情に燃えるより、結婚するほうがよいからです。
10、すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。
11、もし別れたのなら、再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻と離婚してはいけません。
12、そのほかの人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。
13、また、女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。
14、なぜなら、信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また、信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったら、あなたがたの子どもは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。
15、しかし、信者でないほうの者が離れて行くなら、離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫あるいは妻は、縛られることはありません。神は、平和を得させようとして、あなたがたを召されたのです。
16、妻よ。あなたが夫を救えるかどうか、どうして分かりますか。また、夫よ。あなたが妻を救えるかどうか、どうして分かりますか。
はじめに—
コリント人への手紙は7章に入り、ようやくパウロはここからコリントの教会から書き送られてきた質問に答えます。コリントの教会からの1つ目の質問は「性と結婚」についてでした。
どうしてこのような質問がパウロに寄せられたのかと言うと、何度も申し上げておりますが、コリントの町の道徳的水準の低さからでした。当たり前のように姦淫(結婚外の性関係)が横行し、また男色(同性の性関係)があり、しかもそれらは偶像礼拝とも深く関わっていたものですから、それらはこの世の普通となってしまっていました。ほとんど誰も変だ、それはおかしい、間違っていると思わなくなってしまっていた。もしこの時代にテレビがあったら、今の時代と同じように、普通にそのようなドラマが制作され放映されていたことでしょう。恐らくコリント人も、性と結婚に関してそれは良い、それは良くないと分かっていた(分けられた)と思います。人間には神が与えられた良心というものがあるからです。人を殺してはいけないということは誰かが教えなくても自然と分かっているように、性や結婚に関しても何が良くて何が悪いのか分かっていたのでしょう。ところが偶像礼拝が深く関わり(それはつまり試みる者、サタンとの深い関わりですが)、この世は人の目が惑わされ、良心が曇らされ、姦淫も男色も当たり前、悪いことではない、何も悪いと思わない。かえって自由な性を楽しまない者の方が愚か、時代遅れ。自由な性を楽しむ者が高められる、もてはやされる。批判しようものなら迫害される。そんな世になってしまっていたのでしょう。まさに「今は終わりの時。暗闇の力」を思わせます。
そのような「終わりの時」を思わせるようなコリントの町に立つ教会には、結婚について大きな意見の対立がありました。あちらこちらからの噂としてパウロの耳に届いていた、世に流行していた極端なまでの快楽主義に立つ者。その反動として、これまた極端なまでの禁欲主義に生きなければとする者たちがおり、この2つの立場の者たちが対立していたというわけです。そして中でも極端なまでの禁欲主義の者たちは悩んでいたのでしょう。今の夫婦の関係を続けても良いものかと。なぜならコリントの教会は立って間もない教会ですから、クリスチャンになる前に結婚した人たちも当然ながら大勢いたからです。配偶者の片方が救われてクリスチャンになり、もう片方が未だ未信者というパターンも多々あったからです。それでこの世の流れに疑問を持ち、悩み、極端な聖さに対する考えを持ち、極端な禁欲主義の立場に立とうとする人たちは、このまま未信者との結婚生活、性関係を続けて良いものかと悩み、もしかしたらすでに離婚してしまっていた夫婦もいたのだと思われます。そこでコリントの教会で混乱が起きてしまった。終わりの時のサタンの巧みな攻撃は、このような形でもなされるのですね。彼らはパウロに質問をし、正しい教えを求めたのでしょう。
パウロの答え
7章1節 さて、「男が女に触れないのは良いことだ」と、あなたがたが書いてきたことについてですが、
1節から「さて」と、パウロはいよいよ手紙の質問に対する回答へと入って行きます。この1節は疑問文として受け取ることも可能なのですが、パウロの1つの大前提が語られているところです。コリントの聖徒によって記された疑問や質問のベースが「男が女に触れないのは良いことだ」だったのでしょう。その意見に対して、パウロの大前提も同じく「男が女に触れないのは良いことだ」でした。
ここの「触れる」というのは、「肉体的に知る」という意味のギリシャ語で、「性関係を持つ」ということ。つまりパウロは、独身が良いことだと言っているのです。ただし「良い」とは、ここでは「必要である」とか「道徳的にまさっている」という意味ではありません。「おすすめできますよ」とか、9節の「〜よりも良い」「〜だったらこっちの方が良い」というような意味です。
しかし本来結婚というのは、神がこの世界を創造された時に、神の栄光と人類の幸福のために定められたものです。そして結婚は神の祝福です。なぜなら神と人との関係の「型」でもあるからです。なので聖書は「結婚がすべての人の間で尊ばれる」ようにと命じています。神と人とがお互いに約束をする。「常に愛し、敬い、慰め、助けて、その健康の時も病の時も、順境の時も逆境の時も、常に真実で愛情に満ち、いのちの限り堅く節操を守ります」と、ある種「契約」を結んでくださるのです。そして深くお互いを知るという親密な関係となる。
パウロは聖書の教えに反しているのでしょうか。決してそうではありません。コリントという特殊な場所で教会生活の乱れを防ぐという実際的な目的があって、その目的の中で教えているのだということを、私たちは知らなければなりません。パウロは独身が良いことだ、おすすめできると語った後、だからと言って結婚生活が悪いという意味ではないと、すぐに補足します。
結婚の許容
7章2節 淫らな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。
「独身で過ごせる人はそうすべきであるが、独身を強要してはならない。それは『淫らな行いを避けるため』にです」。パウロは独身主義が良いことに同意してはいるものの、それには誘惑も多くつきまとっていることを指摘します。誘惑とはサタンが用いる常套手段です。人の目と心を神から逸らし、滅びへと導こうとするものです。事実、コリント人を取り囲む環境には不品行があちらこちらにはびこり、横行していました。まさにはびこっていたのです。未婚の男女がそれぞれ性的な聖さを保つのは難しく、また他人を結婚まで性的に聖いままでいるように説得するのも容易ではなかった。説得しようものなら愚かだと馬鹿にされてしまう。これもまた今の私たちを取り囲む環境と変わりありませんね。
2節で用いられている「淫らな行い」というギリシャ語の名詞は複数形が用いられています。それはその行為が多くあるということを示しています。淫らな行い、不品行への誘惑という観点では、多くの人にとって一生独身で通すことは難しいでしょう。コリントに蔓延した性的不道徳と淫らな行いは、独身の賜物を受けなかった人にとっては大きな誘惑でした。独身の賜物(神から特別に与えられた恵み)というのは、「自制」です。それほど多くの誘惑に直面する以上、独身の賜物「自制」を受けなかった人は「それぞれ」結婚する方が良い、おすすめできますと言うのです。そしてここでは命令がなされます。1人の男に1人の妻。1人の女に1人の夫。一夫一妻、男女の結婚の命令があります。おすすめではありません。
7章3節 夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対し②義務を果たしなさい。
7章4節 妻は自分のからだについて権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように、夫も自分のからだについて権利を持ってはおらず、それは妻のものです。
ここでパウロはお互いに相手に果たす義務があると言います。しかし片方を犠牲にしてまで、その義務を強調しているということではありません。当時の男尊女卑という社会の状況を考えるなら、この勧めは実に画期的でした。夫婦関係に関する新しい次元の教えでした。結婚というのは、夫と妻、それぞれに性的誘惑に立ち向かうことのできる力を与えるのです。それは男女ともに、同じように性的誘惑があり、立ち向かうことのできる力を必要としているということです。
7章5節 互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのならかまいません。これは、あなたがたの自制力の無さに乗じて、サタンがあなたがたを誘惑しないようにするためです。
当時のラビは、夫婦が離れて過ごさなければならない期間を定めていました。進歩的なヒレル派は1週間、保守的なシャンマイ派は2週間と定めていました。しかしパウロの勧めは、そのようなタブーとは異なります。夫婦が離れずに一緒にいることが最も理想的だと教えます。コリントの教会の中の厳格なグループには、夫婦の決定によって一定期間離れて祈りに専心しようとしていた夫婦もいたのでしょう。パウロはそのことをも否定はしません。聖くいられるためには、祈りに専心することも大事で、夫婦が一緒にいることも大事。そのどちらも、この世にあって誘惑に立ち向かうことのできる力、打ち勝つことのできる力となるからです。
それぞれの賜物のままに行いなさい
7章6節 以上は譲歩として言っているのであって、①命令ではありません。
7章7節 私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、一人ひとり神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。
恐るべき罪である淫らな行い、性的不品行を避ける手段として、「自分の妻を持ち」、「自分の夫を持ちなさい」と言い、7章6節で、これは「譲歩であって、命令ではない」と言います。それでもやはりパウロは独身が良いことだ、おすすめできると言いたいのでしょう。その理由はこの後少し顔を出しますが、明らかにされるのは今日の箇所よりもう少し後の26節あたりからです。
パウロの願うところは、すべての人が彼のように独身で過ごすことです。
ところで、パウロはこれまで1度も結婚したことがなかったと思われますか。実はそれは考えにくいことなのです。ラビによって律法を注解された「ミシュナー」によって、ユダヤ人男性は結婚して子どもをもうけるように定められていました。パウロはもともと律法に厳格な派に属していましたし、律法に超忠実な男でした。パウロはある時期結婚していたと考えるのが自然と言えるでしょう。そしてもしパウロがサンヘドリンの議員だったとすれば(使2610参照)、パウロは確実に結婚していたはずです。しかし、この手紙を書いた時点で結婚していなかったのは確実です。それはつまり、パウロは男やもめだったか、妻に去られてしまったかでしょう。悲しいかな、妻に去られてしまったのだとしたら、それはパウロがクリスチャンになった時点であったのかもしれません・・・。
そのパウロには数々の特別な賜物がありました。つまり神から与えられた恵みがありましたが、その1つが独身を可能にする賜物でした。自制です。これをいただいていない人は「終わりの時」、未婚を通すべきではないのです。
結婚すべきかせざるべきかの問題。それは1つの同じ決まりを全員に当てはめて決めるわけにはいきません。どちらの賜物を神がくださっておられるのかを、それぞれが考えなければなりません。それは誰からも決めつけられるべきものでもありません。結婚も、独身も、同様に神の賜物(神がその人に与えられる恵み)なのです。そしてそれはサタンの試みに打ち勝ち、主に心から従って行くことを可能にするものなのです。
結婚しない者とやもめに対する勧め
7章8節 結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるなら、それが良いのです。
7章9節 しかし、自制することができないなら、結婚しなさい。欲情に燃えるより、結婚するほうがよいからです。
「やもめの女性」とわざわざ記されているのは、恐らく彼女たちには特有の立場の弱さと、再婚したいという当然の欲望があるからなのでしょう。パウロは結婚していない人、やもめの人は皆、パウロ自身がしているように、現在の状態を保つ方が良いことなのだと語っています。しかしそれもまた、自制の賜物を持っているか否かにかかってきます。神がその賜物をお与えになっていないなら「結婚しなさい」と言います。これは命令です。なぜなら「欲情に燃えるより、結婚するほうがよい」からです。恐らくコリントの教会の中の禁欲主義者たちは、現在独身の人、特にやもめの女性に「結婚してはいけない」と命令したのでしょう。しかしパウロは、それが逆に性的不道徳につながることを案じました。パウロは少し前の6章9節で、「不品行な者は神の国を相続できない」と語ったばかりです。
結婚した人たちに対する勧め
7章10節 すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。
7章11節 もし別れたのなら、再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻と離婚してはいけません。
パウロは結婚した人たちに対しては、妻は信者である夫から「別れては」ならず、夫も妻を「離婚しては」ならないと命令します。これを命じるのは私ではなく主ですと念を押しています。そしてすでに別れたのなら、再婚せずにいるか、あるいは夫婦が離婚せずに和解することを勧めます。
パウロは、これは自分の実体験から出たものではなく、主の命令であると言うのです。パウロのこの勧めの根拠は、主の命令にあるのです。かつてイエス様が、たとえばマタイの福音書19章で教えておられたことに根拠がある。しかしパウロは、そのイエス様の命令を聞いていませんでした。復活のイエス様と衝撃的な出会いをし、劇的に救われてからすぐに、だれにも会わずに荒野に退き、3年間も一人でそこにいました。誰からもイエス様の教えを教えてもらってはいませんでした。それなのになぜ知っていたのでしょうか。クリスチャンになった時点で妻に去られてしまった、その自分の実体験をもとに、みことばに聞き、必至に祈り求め、復活の主から生きた答えをいただいたからでしょう。そしてパウロは、心に真の平安をいただいたのではないでしょうか。
残りの人々に対する勧め
7章12節 そのほかの人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。
7章13節 また、女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。
「そのほかの人々」とは、キリスト教の結婚で一緒になったのではない人たちのことです。ここでは、夫婦の一方が不信者である場合の離婚が取り扱われています。教会には当然、クリスチャンになる前に結婚した人たちもいたわけです。そしてもし、片方のみが信仰者になった場合に問題が生じました。彼らの中には、不信者とこのまま夫婦であり続けるべきかと悩んでいた人がいたようです。
ここでは先ほどと違って、「これを言うのは主ではなく私です」と断っています。しかしこの指示がパウロ自身から出たものだから、権威の点で劣るという意味ではありません。「この私が言うのです。クリスチャンになって妻に去られたこの私が言うのです。苦しみの中、荒野で必至に祈り、主と深く交わり、復活の主の罪の赦しをいただき、主から答えをいただいた、平安をいただいた、この私が言うのです。この私をとおして、主はあなたがたに命じているのです」。
もし、信者でない妻が、イエス・キリストを信じて従う夫との結婚の継続を「承知している」「同意している」「望んでいる」なら、その妻と離婚してはならないのです。その逆も然り。信者でない夫が、イエス・キリストを信じて従う妻との結婚の継続を「承知している」「同意している」「望んでいる」なら、その夫と離婚してはならないのです。
7章14節 なぜなら、信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また、信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったら、あなたがたの子どもは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。
信仰者は「聖徒、聖なるもの」、つまり神によって神のために特別にこの世から「取り分けられている」者です。「聖められている」「聖別されている」というのは、道徳的に立派ということではありません。神との関係です。神のものとされているということです。
イエス・キリストを信じ、神と契りを結んでいただき、神のものとされたその人の状態は、今も異教徒である配偶者と結婚関係を継続しているからといって無効にされることはありません。かえって、異教徒、不信者の配偶者がイエス・キリストを信じ従う配偶者を通して「聖なるもの、神のもの」とされているのです。だから離婚してはならない。さらに信仰を持つ親によって、子どもたちも「聖なるもの、神のもの」とされるのです。しかしこれらは、イエス・キリストを信じる配偶者がいるならば、不信者の配偶者と子どもが救われるという意味ではありません。ただ、イエス・キリストを信じ従う配偶者から信仰の影響を受けて、やがて信仰をもつようになって救われる可能性があるということです(あるいは救われた可能性があると言っても良いでしょう。神のみぞ知るです)。「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます」(使1631)です。病気がうつるという感覚で、汚れとか罪が伝染するというイメージは湧きやすいと思いますが、しかし聖さというのも確実に伝染するのです。神との交わりからあふれる本物の祝福というのは、直接その人だけに制限されるものではなく、神の恵みはもっと大きく、深く、高く、広いものですから、他者にも及ぶのだというのが、聖書の原則です。
信者でない配偶者がイエス・キリストを信じ従うことに反対しないならば、教会に行くことに協力的であれば、当然のことながら霊的な良い影響を受けるはずです。また、十分な年齢に達して自分で責任を取ることができるようになるまでは、信仰者を親に持つ子どもはクリスチャンと見なされるべきだと思います。親も教会も、その子をクリスチャンと見なし、しっかりと信仰を養って行くべきでしょう。
7章15節 しかし、信者でないほうの者が離れて行くなら、離れて行かせなさい。そのような場合には、*信者である夫あるいは妻は、縛られることはありません。神は、①平和を得させようとして、あなたがたを召されたのです。
7章15節をご覧ください。「しかし」とパウロは言います。信者でない者が、結婚をこのまま続けようとは望んでいないなら話しは別だと言います。「離れて行く」は「自分で自分を切り離す」というものです。もし未信者である配偶者が離婚を望むならば、自分で自分を主との関係から切り離すのであるならば、クリスチャンである配偶者は「縛られる」ことはありません。これは離婚して良い、自由に再婚して良いという意味でしょう。「神は、平和を得させるために、あなたがた(私たち)を召された」のであり、決して苦しめるために召されたのではありません。
信者と未信者との結婚に関するこの種の問題に関して、どこで線引きをするのか。それは「平和」の一助になるかどうかで決まるのです。神との平和、相手との平和。ある場合は、それは結婚の継続であり、別の場合は結婚は終わりだとする異教徒の配偶者の決心を受け入れること。どちらにせよ、そこに平和がなく争いや戦いがあるなら、引きずられてしまうのです。世に飲み込まれてしまうのです。地の塩が塩けを失ってしまうのです。配偶者との結婚生活のせいで、主のことを考えず、主に喜ばれないことを優先してしまう、そのような弱さが私たち人間にはあるからです。「常にあなたを愛し、敬い、慰め、助けて、健康の時も病の時も、順境の時も逆境の時も、常に真実で愛情に満ち、いのちの限り堅く節操を守ります」という主との誓いをすぐに破って捨ててしまうような者だからです。
7章16節 妻よ。あなたが夫を救えるかどうか、どうして分かりますか。また、夫よ。あなたが妻を救えるかどうか、どうして分かりますか。
もし結婚が継続したとしても、信仰者が信者でない配偶者を救えるかどうかは、定かではない。このみことばから、まったく逆の結論が引き出されてきました。1つは「楽観的」な結論。結婚は未信者の回心を願い、できるだけ長く継続すべきである。「時が来れば、相手が救われないと、誰が言えるだろうか」と。しかしそれは、これまでの文脈で考えるならば、相手が信仰に反対していない場合に限ってのことです。これまでの文脈を考えるならば、これとは逆でしょう。信仰に反対し、自分から自分を結婚生活から切り離そうと固く決心している、その結婚にしがみつく先の結果は分からないのです。それがその人に信仰を捨てさせ、神との契約を破棄し、永遠のいのちを放棄する結果になる恐れがあるならば、主は離婚を赦される。あくまでも主の御心は、離婚してはならないことではありますが、「わたしを遣わされた方のみこころは、わたしに与えてくださったすべての者を、わたしが一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。わたしの父のみこころは、子を見て信じる者がみな永遠のいのちを持ち、わたしがその人を終わりの日によみがえらせることなのです」(ヨハ639-40)と、そう言われる主は、ご自身の十字架によって離婚を赦されるでしょう。結婚を単なる伝道の手段のようにみなしてはならないのです。イエス様は弟子たちを伝道に遣わす際に、その町で迫害が起こるならば、足のちりをはらってすぐにそこから出て行くように言われました。弟子たちの永遠のいのちを守るためにです。それほど私たちは強くないからです。
しかし主は言われます。「自分に関することについては、できる限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りにゆだねなさい。こう書かれているからです。『復讐はわたしのもの。わたしが報復する。』主はそう言われます」(ロマ1218-19)。平和を保つために、争い戦って永遠のいのちを失うことのないように、もし信仰に反対し、自分から自分を結婚から切り離そうと固く決心する人がいるならば、その人は神の御手に委ねるべきでしょう。神のさばきは「そのなすがままにまかせる」こと。そして全能にして愛なる神だけがその人を救うことができるのです。
以上、パウロの回答を見てきましたが、もう一つ、ここから示されることがあります。パウロは独身でいられるならばそれが良いけれども、恐るべき性的不道徳の罪に陥るよりは結婚する方が良いと勧めました。しかし結婚を単なる伝道の手段のようにみなしてはならないとか、信者と信者でない者の夫婦には離婚とか争いとか、危険な可能性が秘めていると言います。ですから聖書は、そのような可能性がある結婚を良いと認めるはずはないのです。ここでも楽観的な考えがあり、それは牧師の間にまで浸透しているのかもしれませんが、それは「結婚をしてから相手を信仰に導けば良い」というものです。本当にそうでしょうか。それさえもサタンの試みであると言えないでしょうか。確かに結婚してから信者でない相手が救われたという例は確かにありますし、それはとても素晴らしいことではありますが、保証がまったくない点であくまでも結果論に過ぎません。地の塩としての塩けを失ってしまう可能性もあったはずです。そのような危険があるならば、そのような結婚を喜んで勧めるわけにはいきません。その結婚を諦めるか、相手がクリスチャンになってから結婚するかです。
色々なパターンが語られて来ましたが、根本的に聖書は私たちに、結婚生活の原則として、終末の時にしっかり備えることが基本だと教えています。今は終わりの時。暗闇の力。サタンが支配し、目を惑わす試みが満ちている世。パウロは患難が差し迫り、サタンの試みに打ち勝つように教えるのです。その中での結婚に関する教えです。イエス・キリストの十字架によって、イエス・キリストのいのちによって神のものとされた私たちのいのちを守るための教えです。
もし、結婚に何かしら悩みがある方がおられるなら、また、これから結婚するかしないかについて考えておられる方がおられるなら、そのような方は主の自分への召しとみこころがどこにあるのかを、よく見分ける必要があります。そこで大切なのが、罪を遠ざけるということです。神の召しとみこころが何であっても、神に従っていくことを決断しましょう。独身か結婚かを決めることは、神のみこころに従って各自が決めることです。それぞれが神の召しに従って、神が何を望んでおられるのか、神がこの私をどこに召そうとしておられるのか、神がこの私を召そうとしておられる「平和」とは何なのか、聖霊に導かれ祈りましょう。答えをいただきましょう。それが不可能だと思えることであっても、神が必要とされているならば必ず解決や必要は与えられます。そして教会も聖霊と愛に満たされて、お互いのために祈り支えてまいりましょう。私たちは神の祝福を確実に受け継ぐために召されたのです。