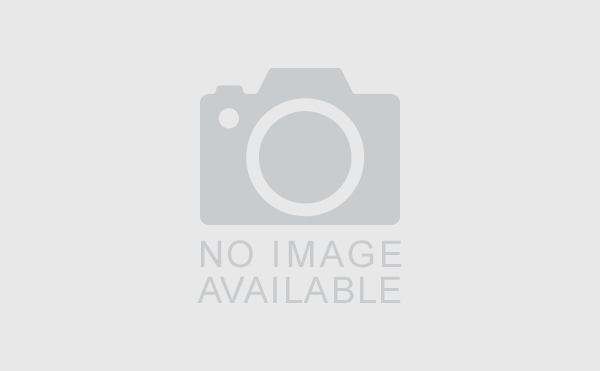2025年8月31日 主日礼拝「自分をわきまえるなら恵みが注がれる」
賛 美
前奏(黙祷)
招 詞 詩篇51篇1〜6節
讃 美 讃美歌84「かみにたより」
罪の告白・赦しの宣言
信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 249「われつみびとの」
聖書朗読 コリント人への手紙 第一 11章27〜34節
説 教 「自分をわきまえるなら恵みが注がれる」
讃 美 讃美歌524「イエスきみ、イエスきみ」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 コリント人への手紙第一 11章31節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
コリント人への手紙 第一 11章27〜34節
説教題
「自分をわきまえるなら恵みが注がれる」
今週の聖句
しかし、もし私たちが自分をわきまえるなら、さばかれることはありません。
コリント人への手紙 第一 11章31節
説教「自分をわきまえるなら恵みが注がれる」
コリント人への手紙 第一 11章27〜34節
はじめに——
先週は人生で2度目の新型コロナに感染してしまい寝込んでしまうという、突如思わぬかたちで夏休みをいただいてしまいました。皆さまには大変ご心配やご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。またお祈りいただき感謝でした。木曜日あたりから少し体調に異変を感じ、金曜日の朝の仕事中にどうしようもなくなり早退させていただき、検査キットを買ってきてもらい検査したところうっすら反応が出てしまい、これはまずいと思い、慌てて日曜日の説教のご奉仕をしていただける先生を探してお願いし、それから検査をしてもらおうと病院に行くと、「コロナはもう普通の風邪ですから」などと言いながら、病院内では相変わらずしっかり隔離され、また防御服で仰々しく身を包み、なるべく体に触ろうとしない看護師さんの姿を見て「本当かよ」と心の中で突っ込みながら検査結果を待っていると、「ご立派な反応が出ていますよ!」と遠くから叫ばれ、やっぱり…と観念するとたちまち体調が悪化し、寝込んでしまったというわけです。それから家族にうつしてはいけないと、家には帰らずに教会の2階の奥の部屋で寝ていました。それは私にとって、恵みの安息の時ともなりました。確かに体は非常に具合が悪く、動けないほどではありましたが、動けないからこそただ横になり、天上を見つめたり窓から見える空を見上げたりする中で、自然と思いは内へ内へと入って行くのです。いわゆる「自己吟味」が始まるのです。嫌でも自分のことを考えてしまうのです。日曜日の奉仕も休まなければならない。色々な人に迷惑をかけてしまう。情けない。そこから始まって、これまでの自分までも振り返り、失敗したこと、ダメな自分、情けない自分、神に背き好き勝手なことをして罪を犯してしまった罪深い自分の姿が次々に思い起こされて来る。人に言われた大小様々なひどい批判の声、私の人生までも否定されるような声が思い起こされ聞こえてくる。私は本来弱い人間ですから、決して平気ではありません。しかし不思議なことに、そこから湧き出る思いというのは、絶望や悲しみではなく、恨みつらみでもなく、平安なのです。こんな私を主が見つけて選んでくださった。罪深い一つ一つの出来事に、イエス様を通しての赦しがあったのだ、赦しがあるのだ。自分の思い通りにはならなかったけれども、それによって主は私を様々な危険から守り、正しい方向に導いてくださったのだ。私は確かに赦されているのだ。愛されているのだ。そして今があるのだという感謝の思いが溢れるのです。心が震えるような、いのちが満ちてくるような思い、喜びが与えられ、こんな自分でも主が共にいてくださるのだから、これからも生きて行ける、生きて行って良い、生きて行こう、生きて行かなければと、そう思わされるのです。
皆さんも良くご存知かと思いますが、「瞬きの詩人」と呼ばれる坂城町出身の水野源三さん。彼は9歳の時に赤痢にかかり、その高熱によって脳性麻痺を起こし、目と耳の機能以外のすべてを失い、寝たきりの人生を送られた方です。彼がその寝たきりの中で書いた詩があります。会堂の後ろに掲げられている詩です。皆さんもいつも目にしていると思います。私は今回の寝たきりの生活の中で、その詩を何度も思い起こしました。この詩が染みてきました。彼も私と同じような思いの中でこの詩を書いたのだろうかと思いました。「主に愛されて」という詩です。「なんのために生きるのか、わからないときにも、生きなければ、生きなければ。主に生かされているのだから。主に生かされているのだから。行く先はどこなのか分からない道をも、行かなければ、行かなければ。主が先に行かれたのだから。主が先に行かれたのだから。いつわりを言う人や、かたくなな人をも、愛さなければ、愛さなければ。主に愛されているのだから。主に愛されているのだから」。
辛い寝たきりの日々の中で、水野さんの思いも内へ内へと入って行ったことでしょう。そこでこのような詩が書けるのは本当に素晴らしいことだと思います。他の誰かや自分の人生を恨み、悲しみ、諦め、嘆くのではなく、いのち、希望、感謝に溢れた詩が、賛美が内側から湧き出てくる。それはこの罪人である私のためにイエス様のからだは裂かれたのだ。イエス様が私のために流された血によって、私は神と完全な和解(仲直り)をさせていただけるのだ。イエス様の復活によって罪に対する完全な勝利、そして永遠のいのちがこの私に約束されているのだ。それをただ信じる者に与えられる神の赦し、何があっても決して変わることのない愛、神との永遠の平和な関係の中に置かれている救われた者に、惜しみなく注がれる主からの祝福でしょう。恵みです。
そこで安息って本当に必要なのだと思わされます。私たちには1週間に1日の安息日が与えられている恵みを覚えます。私たちはその安息日を、せっかくの主の前で安息(何の煩いもなく、くつろいで休むこと)できる恵みの時、機会、チャンスが備えられているのに、それをどのように過ごすのでしょうか。
ふさわしくない参加
さて、コリント人への手紙第一の講解ですが、2週も間が空いてしまいましたが、今日の箇所は前回からのまったくの続きとなります。細かいところは前回の説教をホームページなどで見返していただくと良いと思いますが、大まかに振り返りますと、コリントの教会で執り行われていた秩序がなく、貧しい者や弱い者に対する配慮が全く見られない、見苦しい聖餐式に対するパウロからのお説教でした。パウロは17節で、コリントの集会は、集まること(つまり礼拝)が益ではなく害をもたらすようになっていると批判しました。特に問題なのは、その集まるとき、そこには本来、信仰による教会の一致、また兄弟姉妹が愛し合う姿が現れるはずであるのに、実際にははっきりとした分裂が現れていることでした。パウロは叱責するのです。「あなたがたのイエス・キリストの名のもとに集まるその集会に、そこに信仰はあるのか、そこに愛はあるのかということです。
初代教会では聖餐式が教会の礼拝の中で主要な役割を果たし、中心的・重要な位置を占めていました。聖餐式がメインだったということです。前回ご一緒に学んだところですが、当時の聖餐式は、愛餐会(キリスト者の食事会)とともに記念式典・儀式として行われるものでした。皆が持ち寄った食べ物を聖餐台(卓)に全部並べ、それを皆で分け合って食べました。その中で主イエス様がなさった通りの所作を行い、イエス様が語られたとおりのことを語り、そのように厳かな雰囲気が演出され、聖餐式として執り行われていました。
富む者も貧しい者もともに食事を持ち寄り、主のみわざを覚え感謝し、主にこれほどまでに愛された者同士が愛し合い、分け合って食べる。それが本来の愛餐会・聖餐式でした。ところが、富む者は自分が持って来て1度は主にお献げした食事を「自分の食事」(21)と言って、同席の貧しい者には分け与えず、遅れてくる信者(多くは仕事のために遅れる奴隷信徒だった)を待たずに勝手に食べてしまっていました。美しくない光景。無秩序で配慮のない行動。愛餐会を伴う聖餐式は、実際、天の御国での主の食卓の先取りであり、喜びの食卓ではありますが、コリントのそれは、無制限の喜びに身を任せて飲み食いする姿でした。ドンチャン騒ぎのようだったのでしょうか。そこに信仰はあるのか。そこに愛はあるのか。そのように思わせる聖餐式に対する彼らの醜い態度が見られました。貧しい者、何も持ってこられない者、奴隷であるためにどうしても遅れて来てしまう者が教会の隅に追いやられ、食卓からはぶられ、冷たく扱われる。それによって分裂が生じていた。さらにはそれによって目に見える問題、目に見えない問題が教会に山積していた。
そこでパウロは言います。
11章27節 したがって、もし、ふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主のからだと血に対して罪を犯すことになります。
「ふさわしくない仕方で」は、古い訳では「ふさわしくないままで」であり、それはつまり「ふさわしくない態度で」ということです。
ところで、この「仕方」という語の意味を正しく理解しておられるでしょうか。多くの方は「方法」とか「やり方」だけを思い浮かべるかもしれませんが、他に「他人に対する振る舞い、仕打ち」という意味があります。つまり貧しい者、何も持たない者、立場的に弱い者に対するあなたがたの振る舞い、仕打ちです。仕打ちとまで言うのです。仕打ちというのは不当な扱い、特にひどい扱いを指す言葉です。コリントの教会では貧しい者、何も持たない者、それ故に何も持ってくることが出来ない者、献げられない者、立場的に弱い者に対する「仕打ち」が所々において見られたのでしょう。そしてそれが愛餐会、聖餐式に如実に現れていた。
パウロは言います。「それは、主のからだと血に対して罪を犯すことと見なされる」と。誰に見なされるのでしょうか。他でもない、たましいもからだもゲヘナで滅ぼすことがお出来になるお方、父なる神にです。イエス様はこの方を恐れなさいと言われました(マタ1028)。
「主のからだと血」。罪人のために献げられた主のみからだ。罪の赦しのために流された主の血。イエス・キリストのからだは私たち罪人のために裂かれ、イエス・キリストの血は多くの人々の和解のために流されました。それは父なる神が罪人に注がれる愛とあわれみによるもの。父なる神が取るに足りない弱く貧しい者に注がれる愛とあわれみによるもの。与えられる資格のない者に与えられる恵み。愛されるはずのない者が愛される恵み。霊の親に逆らい、反抗的で、暴言を吐き、霊の親に背を向け自分勝手な道に出て行ってしまった霊的放蕩息子に、それでも注がれ続けられた無償の親の愛。親心。それは注がれる神の心、神の聖なる霊、御霊です。私たちには神の御子イエス・キリストを私たちの罪のために犠牲として裂かれ、私たちとの和解のために神の御子イエス・キリストが血を流されるほどの御霊が注がれているのです。そのことを覚え、主の愛に応え、真実に感謝し執り行われるべき愛餐会、聖餐式が、身勝手で無制限無秩序の喜び、飲み食いだけのドンチャン騒ぎによって冒瀆されていた。主のからだと血、犠牲、愛、救いのみわざを飲食以下の無価値なものとした。
それは「罪を犯すことになる」。このギリシャ語は「裁判を受ける責任がある、死ななければならない、永遠の罪の責任に捕らえられている」という、恐ろしくもはっきりとした意味を持つ語です。「まことに、あなたがたに言います。人の子らは、どんな罪も赦していただけます。また、どれほど神を冒瀆することを言っても、赦していただけます。しかし(あなたに注がれている)聖霊〈御霊・父なる神の愛、親心〉を冒瀆する者は、だれも永遠に赦されず、永遠の罪に定められます」(マコ328-29)。まさにイエス様が言われたとおりです。
コリントの教会では貧しい者、何も持たない者、それ故に何も持ってくることが出来ない者、献げられない者、立場的に弱い者に対する「仕打ち(不当な扱い、特にひどい扱い)」が所々において見られました。富む者、力の強い者の利己的な行動。自分の利益や幸福だけを最優先に考え、他人の都合や気持ちを省みない行動が、教会に分裂と無秩序をもたらしました。そしてそれが愛餐会、聖餐式において特に如実に現れていたのです。
正しい聖餐と警告
そこでパウロは28節でこのように勧めます。
11章28節 だれでも、自分自身を吟味して、そのうえでパンを食べ、杯を飲みなさい。
愛餐会、聖餐式を機会に、自己吟味することが命じられています。「吟味」というギリシャ語は、「試みる、物事を念入りに調べる、考察する、尋問する、罪状を調べただすこと」を意味しています。ここでは聖餐式を機会にして自分自身を吟味しなさいと言われていますが、他のところではこのように命じられています。
【コリント人への手紙第二】
13章5節 あなたがたは、信仰に生きているかどうか、自分自身を試し、吟味しなさい。それとも、あなたがたは自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを、自覚していないのですか。あなたがたが不適格な者なら(本当の信仰者でないなら)別ですが。【ガラテヤ人への手紙】
6章4節 それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば、自分にだけは誇ることができても、ほかの人には誇ることができなくなるでしょう。
11章29節 みからだをわきまえないで食べ、また飲む者は、自分自身に対するさばきを食べ、また飲むことになるのです。
パウロは自分自身を吟味しなさいと教えています。今日の所では、愛餐会、聖餐式にあずかるとき、まず自分自身を吟味しなさいと教えています。先ほども申しましたが、初代教会の礼拝の中心は聖餐式でした。ですから今の私たちに適用するならば、私たちは礼拝、聖餐式を機会にして真実の自分に向き合い、自分の行いや考えなどの善悪を考え直さなければなりません。私たちは、罪人のため、自分のために死なれたというイエス・キリストの犠牲的な贖いを正しく理解しているだろうか。自分の人生の中で主の死にあずかった者として、どのように生きて来たかを再確認する必要があります。そのために一旦立ち止まり、自己吟味をしなければならないのです。
29節でパウロが血には言及せずに、キリストの「みからだ」とだけ言っているのは、聖餐のパンの意味を超えて、キリストのからだとしての教会という概念をもって説明したものと解釈できるのではないでしょうか。
自己吟味。それは自分の信仰についてはもちろんですが、27節からの流れを見ても分かるように、教会として、兄弟姉妹に対してどのような態度であったかを省みるように命じていることが分かります。自己吟味です。他人をさばくのではありません。自己吟味をするならば、自分の「仕方」、他の人に対する振る舞い、仕打ち(不当な扱い、ひどい扱い)が見えてくるでしょう。そしてそれは「罪を犯すことになる」、裁判を受ける責任があること、永遠の罪の責任に捕らえられていることに気づかされることでしょう。そういった罪は、必ず自分の肉体、そして霊的にも確実に悪影響を及ぼすばかりでなく、教会全体に悪影響を及ぼすものとなるのです。なぜそう言えるのか。教会はキリストのひとつからだだからです。
聖徒に対する主の懲らしめ
11章30節 あなたがたの中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちもかなりいるのは、そのためです。
「あなたがたの中に」とは、誰のことを指しているのでしょうか。
1つに、「力(影響力)があり、利己的な人たちの中に」でしょう。自分は力も影響力もないと思われるでしょうか。しかし、自分の弱さも、自分の利益や幸福だけを最優先に考え、他人の都合や気持ちを顧みないで他人に振りかざすならば、それは強力な力にもなり得るのです。
もう一方で、「あなたがたの群れの中に」ということでもあるのではないでしょうか。教会を見渡してみて、せっかく幸いな安息日に教会に来て、礼拝に来ているのに、どこか元気のない人、健全でない人、生き生きとしていない人がいないだろうか。そしてもしいたとしたら、それはただその人だけの責任なのだろうか。その人をさばくのではなく自分自身を吟味してみなさい。どんな自分、その人に対するどのような態度、仕打ちが思い起こされるでしょうか。パウロはそう私たちに問うているように思います。
コリントの聖徒は、愛餐会、聖餐式に参加する時には、並べられたご馳走、裂かれたパンと杯を前にして、自分たちのために贖いとなられたキリストのからだの意味を正しく知り、また、その贖いによってキリストのからだなる教会の一員とされた者として、同じ聖餐にあずかる兄弟姉妹、特に貧しい者、奴隷など弱い立場に立つ兄弟姉妹に配慮すべきでした。私たちも謙遜に悔い改めながら礼拝、聖餐式にあずからなければならないことを覚えさせられます。
11章31節 しかし、もし私たちが自分をわきまえるなら、さばかれることはありません。
ここを直訳するとこうなります。「もし私たちが自分自身を裁いていたなら、裁きを受けることはなかったでしょう」。
パウロは、自分自身を吟味することで、主のさばき、刑罰、永遠の有罪判決を免れると説明します。自己吟味をしてみれば、主に裁かれなければならない自分がいるのです。そして自分の心が自分を責めるでしょう。自分は神に裁かれている、だから今の自分はこんななんだ、祝福から遠く離れていると思ってしまうかもしれません。しかし私たちに注がれている御霊、聖霊は、その思いを悔い改めへと導いてくださいます。そして父なる神は、私たちの砕かれた霊、打たれ砕かれた心を蔑まれず、喜んで両手を一杯大きく広げて受け入れてくださるお方です(詩5117)。さらには真実の神はこのように約束してくださっています。「もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、(イエス・キリストにあって、恵みにより)その罪を赦し、私たちをすべての不義からきよめてくださいます」(Ⅰヨハ19)。イエス・キリストにあって主との完全な平和な関係をいただいている私たちにとって、さばきと思われることも、実は父なる神の愛とあわれみによる懲らしめなのです。何でも良い、何でも赦そうというのは本当の愛ではありません。悪いことは悪い、ダメと言われること、それが真実の愛というものでしょう。そしてダメと言われる時に、父なる神の心にも痛みがあるのです。あわれみの神だからです。あわれみというのは、断腸の思い、はらわたが千切れるほどの痛みを意味する語です。
11章31節 私たちがさばかれるとすれば、それは、この世とともにさばきを下されることがないように、主によって懲らしめられる、ということなのです。
聖書のみことば、神の約束に聴きましょう。
「あなたは、人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない」(申85)。
「わたしは彼の父となり、彼はわたしの子となる。彼が不義を行ったときは、わたしは人の杖、人の子のむちをもって彼を懲らしめる。しかしわたしの恵みは、わたしが、あなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない」(Ⅱサム714-15)。
「なんと幸いなことでしょう。主よあなたに戒められあなたのみおしえを教えられる人は」(詩9412)。
「わが子よ、主の懲らしめを拒むな。その叱責を嫌うな。父がいとしい子を叱るように、主は愛する者を叱る」(箴311-12)。
「訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなたがたが、すべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって、本当の子ではありません。霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の聖さにあずからせようとして訓練されるのです」(ヘブ12 7-10)。
イエス・キリストを通して、父なる神との完全で永遠の平和な関係にあずかっている私たち。もし主からさばきを受けたとしても、それは破滅に向かわせるためではなく、主の懲らしめをうけることであるのだと、これほどまでに神はみことばをもって示し、私たちを慰め、励ましておられます。ですから私たちは、神の懲らしめが与えられる時も、神の愛を悟るべきです。神のお心、断腸の思いを知るべきです。そして、もし神がそうしてくださらなかったらどうなっていたかを思うならば、悔い改めて神に立ち返ることができるでしょう。そして私たちはそれぞれに、また私たち教会全体は、健全に建て上げられ、自ずと成長させられて行くことでしょう。
そして私自信、改めて次の主のみことばに心震わされるのです。有名なみことばですが、また別の角度から私に迫ってくる思いがするのです。
【ヨハネの黙示録】
3章19節 わたしは愛する者をみな、叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。
3章20節 見よ、わたしは戸の外に立ってたたいている。だれでも、わたしの声を聞いて戸を開けるなら、わたしはその人のところに入って彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする。
結論
11章33節 ですから、兄弟たち。食事に集まるときは、互いに待ち合わせなさい。
11章34節 空腹な人は家で食べなさい。あなたがたが集まることによって、さばきを受けないようにするためです。このほかのことについては、私が行ったときに決めることにします。
パウロは非常に具体的な教えを与え、聖餐式に対する議論を閉じます。これは聖餐式の手順や順序に関する教えではありません。愛餐会、聖餐式で、自分よりも社会的地位が低く、経済的に貧しい兄弟姉妹(つまり、奴隷の信徒)を待つことについての勧めであり、これまで語ってきたことの結論です。当時の教会の中にいた一部の富んだ人たちは、奴隷に仕えられることが当たり前の世に生きていました。その奴隷に仕えることは、恐らく今の私たちが考える以上に困難が伴っていたことと思います。しかしパウロは命じるのです。「待て」と。「待つ」というのは、一部の富んだ人たちが自分を低くし、奴隷である相手に合わせ、奴隷に犠牲的な愛で仕えることでしょう。自分自身をキリストとともに十字架につけることでしょう。その根拠は、やはり聖餐式を定められた主イエス・キリストの十字架の死です。また、待てと命じられる中で自己吟味をし、醜い自分が示され、自分自身が聖餐式にあずかる資格がまったくない存在であることを正しく理解することにより、主がその場に招いてくださったことに正しく応じることができるようになります。私たちは全員が罪人であり、主の晩餐に無条件に恵みによって招かれた客のようなものです。それにふさわしい恐れと感謝、尊敬をもって主の晩餐に臨みたいものです。
残念なことではありますが、教会や聖徒の中には、様々な問題、表立っていない差別的な心や分裂が現実としてあることを認めないわけにはいきません。神の御心にそぐわない、美しくないこの世の無秩序と自己中心的な態度とさほど変わらないことが教会の中にあるのです。
まずは聖餐式を機会に、みことばが命じられるとおりに自己吟味し、これまでの自分までも振り返り、ダメな自分、情けない自分、罪深い自分の姿が次々に思い起こされて来る。人に言われた大小様々なひどい批判の声、誰の声なのか私の人生までも否定する声が聞こえてくる。しかし不思議なことに、そこから湧き出る思いというのは、絶望や悲しみではなく、恨みつらみでもなく、平安なのです。こんな私を主が見つけて選んでくださった。罪深い一つ一つの出来事に、イエス様を通しての赦しがあったのだ、赦しがあるのだ。自分の思い通りにはならなかったけれども、それによって主は私を様々な危険から守り、正しい方向に導いてくださったのだ。私は確かに赦されているのだ。愛されているのだ。そして今があるのだという感謝の思いに溢れるのです。心が震えるような、いのちが満ちてくるような思い、喜びが与えられ、こんな自分でも主が共にいてくださるのだからこれからも生きて行ける、生きて行って良い、生きて行こう、生きて行かなければと、そう思わされる。自己吟味を通して本当の自分に向き合い、自分自身をわきまえ、そして主からの素晴らしい恵み、祝福をいただきましょう。私たちの救いのために十字架で死なれたイエス様の死を理解し、それを受け入れたその信仰によって、そこから生きて行く。そのことを改めて考え、思い巡らす1週間であることを願います。そして次週の聖餐式には、自己吟味によって熱心に悔い改め、心の戸を開き、イエス様を心にお迎えし、ともに食事に与る。そのような幸いな聖餐式となるように備えたいと願います。