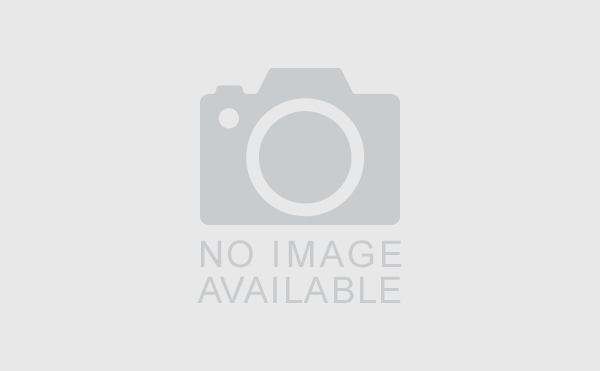2025年4月20日 イースター礼拝「よみがえりの主と出会うとき」
賛 美 「赦すためです」
新聖歌259「聖いふみは教える」
前奏(黙祷)
招 詞 詩篇118篇19〜24節
讃 美 讃美歌146「ハレルヤ」
罪の告白・赦しの宣言
信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 讃美歌242「なやむものよ」
聖書朗読 ルカの福音書24章1~36節
説 教 「よみがえりの主と出会うとき」
讃 美 讃美歌152「陰府のちからは」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 ガラテヤ人への手紙2章20節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
ルカの福音書24章1~36節
説教題
「よみがえりの主と出会うとき」
今週の聖句
キリストが私のうちに生きておられるのです。
ガラテヤ人への手紙2章20節
説教「よみがえりの主と出会うとき」
ルカの福音書24章1〜36節
1、週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。
2、見ると、石が墓からわきに転がされていた。
3、そこで中に入ると、主イエスのからだは見当たらなかった。
4、そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人、近くに来た。
5、彼女たちは恐ろしくなって、地面に顔を伏せた。すると、その人たちはこう言った。「あなたがたは、どうして生きている方を死人の中に捜すのですか。
6、ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられたころ、主がお話しになったことを思い出しなさい。
7、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。」
8、彼女たちはイエスのことばを思い出した。
9、そして墓から戻って、十一人とほかの人たち全員に、これらのことをすべて報告した。
10、それは、マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちとともにいた、ほかの女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、
11、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。
12、しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そして、かがんでのぞき込むと、亜麻布だけが見えた。それで、この出来事に驚きながら②自分のところに帰った。
13、ところで、ちょうどこの日、弟子たちのうちの二人が、エルサレムから*六十スタディオン余り離れた、エマオという村に向かっていた。
14、彼らは、これらの出来事すべてについて話し合っていた。
15、話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいて来て、彼らとともに歩き始められた。
16、しかし、二人の目はさえぎられていて、イエスであることが分からなかった。
17、イエスは彼らに言われた。「歩きながら語り合っているその話は何のことですか。」すると、二人は暗い顔をして立ち止まった。
18、そして、その一人、クレオパという人がイエスに答えた。「エルサレムに滞在していながら、近ごろそこで起こったことを、あなただけがご存じないのですか。」
19、イエスが「どんなことですか」と言われると、二人は答えた。「ナザレ人イエス様のことです。この方は、神と民全体の前で、行いにもことばにも力のある預言者でした。
20、それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して、十字架につけてしまいました。
21、私たちは、この方こそイスラエルを解放する方だ、と望みをかけていました。実際、そればかりではありません。そのことがあってから三日目になりますが、
22、仲間の女たちの何人かが、私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、
23、イエス様のからだが見当たらず、戻って来ました。そして、自分たちは御使いたちの幻を見た、彼らはイエス様が生きておられると告げた、と言うのです。
24、それで、仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言ったとおりで、あの方は見当たりませんでした。」
25、そこでイエスは彼らに言われた。「ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。
26、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから、その栄光に入るはずだったのではありませんか。」
27、それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに説き明かされた。
28、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。
29、彼らが、「一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています」と言って強く勧めたので、イエスは彼らとともに泊まるため、中に入られた。
30、そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神をほめたたえ、裂いて彼らに渡された。
31、すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。
32、二人は話し合った。「道々お話しくださる間、私たちに聖書を説き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。」
33、二人はただちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、十一人とその仲間が集まって、
34、「本当に主はよみがえって、シモンに姿を現された」と話していた。
35、そこで二人も、道中で起こったことや、パンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。
36、これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、「平安があなたがたにあるように」と言われた。
はじめに—幸いな受難週を過ごされましたか?
今年もイースターの朝を迎えました。イースターおめでとうございます。
何度か申し上げておりますが、「おめでとう」というのは、新約聖書の原語であるギリシャ語ですと「あなたは喜びなさい」となります。イースターというのは、もう皆さんご承知のとおり、イエス・キリストが、私たちが神に対して犯してしまった罪の一切を負ってくださり、本来ならば神に対して罪を犯した私たちが神によって罰せられるはずであるのに、神は私たちをあわれみ、ご自身のひとり子であるイエス・キリストをこの世に降らせ、1つも罪を犯さなかったイエス・キリストを私たちの身代わりとして十字架に架けられ罰せられた。イエス・キリストが十字架で味わわれた肉体的、霊的な痛みや苦しみは、いかに罪が悲惨なものかを私たちに知らしめるためであると同時に、いかに神は私たちを愛しておられるかを世に知らしめるためでもありました。イエス・キリストは私たちの罪の一切を背負い十字架に架けられ死んでくださった。このイエス・キリストを信じるならば、私たちの罪は赦され、神との関係が麗しい関係へと回復されるのです。神が私たちを愛するがゆえに、そのように約束してくださっているのです。しかしイエス・キリストは十字架に架けられ死なれ、それで終わりではありませんでした。神はイエス・キリストを3日目によみがえらせられた。これがイースターです。そして神はこのイースターを「あなたは喜べ」と言われ、私たちも互いに「あなたは喜びなさい」と挨拶をするのです。毎年イースターを覚え、このように挨拶をするのです。私たちは一体何を喜ぶのでしょうか。喜ぶことができるのでしょうか。
先週私たちは、受難週を過ごしてまいりました。先週の礼拝ではみことばに導かれ、イエス様がどのような思いの中で私たちのために十字架に向かわれたのかを考え、この十字架に向かわれるイエス様を前にして、イエス・キリストと私との関係を改めて考える1週間としたいと祈りましたが、そのような1週間となったでしょうか。その中で金曜日には受難日を迎え、私たちは十字架に架けられ死なれた救い主を覚えました。そこで私たちは「あなたは、わたしをだれだと言いますか」とイエス様に問うていただけたことと思います。ここでも私たちは考えなければならなかったでしょう。十字架に架けられ死なれたこのお方に、私は一体、何をして欲しかったのか。何をして欲しいのか。
そして今朝、私たちはイエス・キリストの復活を覚えるイースターを迎えました。この「覚える」というのは、ただ思い起こすことではありません。思い起こし、心を奮い立たせ、気を取り直すという、それが「覚える」です。私たちはイースターを覚え、ここでもまた考えなければならないでしょう。向き合わなければなりません。復活のイエス・キリストはこの朝、私たちの前に生きた姿で現れてくださいます。いや、最初からここにこられるのです。私たちの目が私たちの疑いの思いによって塞がれて見えていなかっただけ。今朝、復活のキリストを覚え、目の前にして、私たちはまた覚えるのです。私はこのお方に何をして欲しかったのか、何をして欲しいのか。再び覚えて、心を奮い立たせ、気を取り直すのです。そしてここからまた、聖霊と喜びと力に溢れて、イエス・キリストとともに歩む人生を再スタートさせていただきたいと思います。私たちの人生もまたイエス・キリストの復活に与るのです。
さて今日の箇所は、イエス様がよみがえられた日曜日の朝から夕方にかけての出来事が記されています。
日曜日の朝
週の初めの日、つまり日曜日の明け方早く、彼女たちはいても立ってもいられず、準備しておいた香料を墓に持って来ました。ここの「彼女たち」というのは、10節を見ると分かるのですが、それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちとともにいた他の女たちでした。彼女たちはみな、イエス様に悪霊や病気を治してもらった人たちで、自分の財産をもってイエス様と弟子たちに仕えて来た人たちでした。彼女たちは逃げてしまった弟子たちと違い、イエス様の十字架のそばに立ち、イエス様の十字架の一部始終を見、そして十字架上で語られた7つのみことばを聞いた人たち。さらにはアリマタヤのヨセフによって十字架から下ろされ、下げ渡されたイエス様の遺体が彼の所有する新しい墓に納められた、その一部始終を見ていた人たちでした。金曜日の夕方の葬りの時、イエス様の遺体は幾分急いで墓に納められました。そのため、安息日が過ぎた日曜日の早朝から、彼女たちは準備しておいた香料を携えて墓に向かいました。当時、死体の葬りの化粧は女性たちが担当する習わしだったからです。この時の彼女たちは、イエス様が墓の中からよみがえっているなどとは夢にも思っていませんでした。イエス様が語られた十字架上の7つのみことば、それは「父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです」(ルカ2334)、「まことに、あなたに言います。あなたは今日、わたしとともにパラダイスにいます」(ルカ2343)、「女の方、ご覧なさい。あなたの息子です。ご覧なさい。あなたの母です」(ヨハ1926-27)、「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(マタ2746、マコ1534)、「わたしは渇く」(ヨハ1928)、「完了した」(ヨハ1930)、「父よ、わたしの霊をあなたの御手にゆだねます」(ルカ2346)という、7つのことばの本当の意味が理解できず、死罪にあたらないイエス様が殺されてしまった。どれほど無念であったかと悼み、深い悲しみの中でただ善意をもって一生懸命に葬ろうとしたのでしょう。
彼女たちは「墓の入口からあの石をころがしてくれる人が、だれかいるでしょうか」(マコ163)と話しながら、墓まで歩いて行きました。ところが不思議な光景を目にするのです。墓に着いてみると、心配していた墓の入口を塞いでいた大きな石は、すでに主の使いによって転がされていたのです。彼女たちの知らないところで、すでに彼女たちの心配は主によって解決されていたのです。そんなこととなど全く知らず、彼女たちは道中ずっと心配して歩いて来ていた。
これは私たちの人生にも同じ事が言えるのではないでしょうか。私たちの心配も主はすべてご存知で、その解決がすでに与えられているのに、ずっと心配して時を過ごしてしまい、その時になって「主はすでに、私の思いもよらない最も善い、最も必要な解決を与えてくださっていたんだなぁ」と気づくことがあるのではないでしょうか。
彼女たちが墓の中に入ってみると、主イエスのからだは見当たりませんでした。ちなみに3節で「主イエス」と記されていますが、福音書で「主イエス」と呼ばれるのはこことマルコの福音書16章19節の2箇所だけです。彼女たちの主イエスのからだが見当たらない。そのために、彼女たちは途方に暮れてしまいました。困ってしまって、どうして良いか分からなくなってしまいました。犬のお巡りさん状態。「え、どういうこと!? 私はどうすれば良いの!?」。到底信じられないことが起こり、途方に暮れるという語の中に、「考える、考え込む」といったような意味は含まれません。考えることをせずに、あるいはできずに、ただ途方に暮れ、しばらく時間が経ってしまったのでしょう。人は突然の信じられない出来事が起こると何も考えられなくなってしまうのかもしれません。ただ途方に暮れてしまう。しかし主は、そのような人に一番良いタイミングで、ふさわしい方法でメッセンジャーを遣わしてくださいます。
御使いは彼女たちに問いました。「あなたがたは、どうして生きている方を死人の中に捜すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられたころ、主がお話しになったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう」。そして彼女たちはイエス様のことばを思い出しました。「人の子」とは、イエス様がご自分を指して言われたものです。当時「救い主・メシア」というのは、政治的な意味合いが色濃くあり、ローマの圧政から解放し(ローマをやっつけて)、イスラエル王国を再建する者という意味合いを持っていたので、ご自分がそのような政治的な意味におけるメシアと混同されることを避けるために、その当時だれも使用しなかった「人の子」という表現をわざわざ用いて、ご自分のメシア性を表現しようとされたものです。
御使いは問うのです。そして彼女たちは問われるのです。問われて、イエス様のみことばを思い出して、そして考えさせられて、気づかされて、また考えて、また気づかされてを繰り返し、自分にとっての本当の必要を見いださせ、それを主に求めさせようとされる。それは私たちが「デボーション」と呼ぶものでしょう。みことばを思い巡らし、祈り、神との関係を深めるデボーション。彼女たちはデボーションの中で、自分たちが本当にイエス様に求めていたことに気づいたのではないでしょうか。本当には何をイエス様に求めて、イエス様を愛し仕えて来たのか。悪霊や病気が癒やされた後も、それでもなおイエス様に仕えて来たのはなぜなのか。それは「罪の赦し」でしょう。「罪の赦しによる救い」でしょう。
実は人は「赦しているよ」という言葉を聞きたいのです。そして心から救われたいのです。私にも身に覚えがあります。皆さんはどうでしょうか。はじめは苦しみの中、挫折の中、ただ漠然と幸せになりたくて、この世的に言えば御利益を求めて、神を求めて教会に来ました。しかし実際に私を救ったのは、御利益ではなく「赦しているよ」という神のことばでした。そのことばを聞いて、私は心から救われた、やっと解放されたのです。教会に来て活き活きと喜んで生きている人というのは皆、この世的な御利益ではなく、神からの「赦しているよ」ということばを聞いている人でしょう。
「あなたがたの中で、罪を犯したことのない者が石を投げなさい」。イエス様が周りに集まった人たちにそう問いかけると、そこからだれもいなくなりました。罪を犯したことのない人などいないのです。負い目のまるでない人などいないのです。
この時も、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリア、ヘロデの関係者であるヨハンナ、かつて自分の息子のために勝手な願い事を申し上げてしまいイエス様にいさめられてしまった女性。イエス様に仕えて来た女性たちの中に、自分はここに存在していてはいけないのではないかという気持ちにさらされていた人がいたのかもしれません。私たちの中にも、自分の至らなさ、愛の足りなさ。いつも人に迷惑をかけてしまう。負担をかけてしまっている。約束が守れずに、言ったことをやらない自分がいる。祈ったこともやめられない罪がずっと続いている。赦せない自分がいつもいる。赦されないであろう自分がいつもいる。自分ではどうすることもできない。実はどこかでこの不安を抱えてうずくまるように今日もここにいる。だからこそ誰かに「赦しているよ」と言ってもらいたい。「もう赦したよ」、この言葉を聞けたらどれほど良いだろうか。そして「神よ、私の負い目をお赦しください」と、そのように祈る時、そこで十字架の上で祈られたイエス様の声が聞こえてくるのです。十字架で死なれたけれども、よみがえられ、今も生きていてくださっているイエス様の声が聞こえてくるのです。「父よ、この者をお赦しください。この者は、自分が何をしているのかが分かっていないのです」。その後で「わたしもあなたを罪に定めない。さあ、ここから立って行きなさい」と、今も生きていてくださっているイエス様の声が聞こえてくるのです。たとえ誰かに赦されなくても、たとえ自分が赦せなかったとしても、神は赦してくださる。十字架の赦しは小さくないからです。私たちの思いをはるかに超えた神の私たち罪人に対する愛と赦しなのです。神の赦しこそが、私たちに永遠のいのち、活き活きと生きられるいのちを与えることができるのです。
24章9節 そして墓から戻って、十一人とほかの人たち全員に、これらのことをすべて報告した。
24章10節 それは、マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちとともにいた、ほかの女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、
24章11節 この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。
彼女たちは驚きと喜びの中で一部始終を報告しました。しかしイエス様の十字架を直前にして、イエス様を裏切り逃げてしまった弟子たちは、この話しをたわごとのように思い、彼女たちを信じませんでした。
11節にある「この話」は、8節にあるイエス様の「ことば」と同じ語が用いられています。この話し、イエス様のみことばを、弟子たちは「たわごと」のように思ってしまったということを表しています。「たわごと」は、新約聖書の中でここだけに登場する「精神錯乱の人のうわごと」という医学用語です。それは信じるに値しない愚かででたらめな話。弟子たちは彼女たちの「この話」をそのように扱っただけでなく、実はイエス様の「ことば」をも、そのように扱ってしまったのです。
しかしイエス様を3度「知らない」と言ってしまい、イエス様に見つめられたペテロは、立ち上がり走って墓まで確かめに行きました。自分の失敗に諦めず、それでもイエス様と関係を求めている人というのは、イエス様のみことばをたわごととせずに、確かめに行くのでしょう。求めるのでしょう。私たちも求めているでしょうか。それともどこかで「たわごと」としてしまっているでしょうか。
12節に、「ペテロはこの出来事に驚きながら自分のところに帰った」とあります。「自分のところに帰った」とは、少し不思議な表現です。前の訳、また他の訳では「家に帰った」となっています。33節によると、家というのは弟子たちが集まっていた家でしょうか。しかし直訳すると「彼自身のところに帰った」です。ペテロは驚きの出来事を見て、自分のところに帰ったのです。ひとりじっくり向き合って、じっくり考えたのです。イエス様とは何者なのか。私はこのお方に何をして欲しかったのかを思い巡らせたのではないかと思います。そこによみがえられたイエス様が現れてくださいました。34節に弟子たちが「『本当に主はよみがえって、シモン(ペテロ)に姿を現された』と話していた」とあります。またⅠコリント15章4〜5節には、イエス様は「三日目によみがえられ、ケファに現れ、それから12弟子に現れた」と記されています。イエス様はペテロに出会われ、何を言われたのでしょうか。それはやはり「赦しているよ」ではなかったでしょうか。
さて、もう1組、自分のところに帰った人たちがいました。同じ日曜日の午後のことです。
日曜日の午後
ちょうどこの日、弟子たちのうちの2人が、エルサレムから60スタディオン(11㎞)余り離れた、エマオという村に向かっていました。「自分たちのところ」に向かっていた彼らは、十字架に架けられ死んでしまったイエス様に失望して、弟子であることを止めようとしていたのでしょうか。
彼らはおもに空っぽになった墓の謎について話し合ったり、論じ合ったりしていました。復活信仰がないところでの復活論争というのも滑稽ですが、しかしイエス様の復活というのは、この時から今に至るまで、世の人々の間では変わらず疑いや議論の的であるのでしょう。
時には熱い議論となっていたそのただ中に、イエス様の方から彼らに近づき、そしてともに歩んでくださいました。自分の道を行く彼らの同伴者として。人生の同伴者としてイエス様は歩んでくださる。しかし、ともに人生を歩まれる方が彼らには見えません。その歩みの中で、イエス様は問われます。答えを求められます。イエス様の問いは、彼ら自身に、彼らの失望の原因を彼らの口から語らせるものでした。
彼らは、イエス様が行いにもことばにも力のある預言者であったこと、祭司長や指導者たちが訴え出てイエス様を死刑に定めて十字架につけてしまったこと、自分たちはこのイエス様がイスラエルを救う方であると期待していたことを語りました。彼らがイエス様にかけていた期待は、政治的、地上的な救い主としての期待であったことがイエス様の問いによって明らかにされました。そして彼らが一番戸惑っているのは、葬られた墓からイエス様のからだが消えてしまったことでした。ユダヤのメシア信仰では、メシアはたとえ死んでも、死んだそのからだをもって人々を救う指導者としてこの世に再び現れるとされていました。そのからだが消えてしまった。それでは一体どうなってしまうのだろうか。
24章25節 そこでイエスは彼らに言われた。「ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。
24章26節 キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから、その栄光に入るはずだったのではありませんか。」
24章27節 それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに説き明かされた。
実は旧約聖書のどこを切っても、金太郎飴のようにイエス・キリストと、イエス・キリストによる救いのことが証言されているのです。そして旧約聖書で証言されているイエス・キリストによる救いというのは、政治的・地上的な救いではなく、この世的な御利益による救いではなく、「罪の赦しによる救い」のことです。
彼らの目的地であるエマオの村に近づくと、イエス様はまだ先に行こうとされました。ここでもし、この2人の弟子がイエス様に無理に願って一緒に泊まってくださるように求めなかったならば、イエス様は彼らと一緒に家に、12節のところで言う「彼のところ」に入ることはなさらなかったでしょう。
彼らは食卓に着いた時、主人の位置にイエス様に座っていただきました。道々共に歩まれるイエス様の話しを聞きながら、次第にイエス様に対する思いが変えられていったのでしょう。彼らは食卓についても、イエス様に注目していました。そしてイエス様がパンを取って神をほめたたえ、それを裂いて彼らに渡された時、彼らの目が開かれ、ずっと共に歩まれ、ずっと語られていた方がイエス様であることが分かりました。ふとイエス様の手の傷跡が目に留まったのでしょうか。パンを裂いて渡す仕草を見て分かったのでしょうか。祝福の祈りのことばによって目が開かれたのでしょうか。いずれにしても、イエス様が道々語ってくださったみことば、旧約聖書の証言が、彼らを復活の主イエス様に導く結果になったこと、そして彼らに確信を与えたことは事実です。彼らの旧約聖書の証言から得た確信とは、やはり罪の赦しによる救いでしょう。そして彼らもまた罪の赦しを必要としていた。「赦しているよ」という生きた言葉を必要としていた。そして彼らはまさに、イエス様から一番聞きたかった、一番求めていた「赦しているよ」という神のことばを、旧約聖書のみことばによって導かれ、復活の救い主イエス様から聞いたのです。聞いて確信することができたのです。それは決して人間的な努力によるのではありませんでした。恵みによってまことの救いへと導かれたのです。
24章32節 二人は話し合った。「道々お話しくださる間、私たちに聖書を説き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。」
これこそ本当の救いでしょう。私は赦されたかった。そして神に赦されたのだという不思議な平安が心に満ち、どこからともなく喜びが溢れ出てくるのを感じる。イエス様の姿が彼らには見えなくなりましたが、もうそこに失望はありません。主は生きておられる。主は今も生きておられ、この私の人生をともに歩んでくださっている。その確信をもって二人はただちに立ち上がり、エルサレムに戻りました。
すると、十一人とその仲間が集まって、「本当に主はよみがえって、シモンに姿を現された」と話していました。そこで二人も、道中で起こったことや、パンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話しました。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、「平安があなたがたにあるように」と言われました。復活のイエス様は彼らの前に生きた姿で現れました。いや、最初からそこにおられたのでしょう。
この後、イエス様は弟子たちを信仰の原点であるガリラヤへと導かれます。弟子たちはひとり、またひとりと立ち上がり、挫折の中から復活し、ガリラヤへと向かって行きました。そこでまた生きておられる主と出会い、主によって宣教へと遣わされて行くことになります。イエス・キリストの復活という信じられない知らせは、自分という家に閉じこもり、周りを見えなくさせていた弟子たちの目を開かせるものとなりました。そして彼らの耳を開き、「赦しているよ」という生きた御声を聞かせるものとなりました。そして弟子たちをそこから立ち上がらせ、再び歩み出させ、活き活きと自分の人生を再び歩み出させるものとなりました。
私たちもまた、イエス・キリストの復活を覚えなければなりません。特別にイエス・キリストの復活を覚えるイースターばかりでなく、いつもイエス・キリストの復活を覚えるべきです。覚えるというのは、ただ思い起こすことではなく、思い起こして、心を奮い立たせ、気を取り直すことです。それこそが私たちにとっての復活となるのです。確かに復活とは、イエス様が再臨された時に与るものですが、復活は決して遠い未来の話しだけではありません。復活のイエス・キリストが今も生きて私たちの人生をともに歩まれる。その中でいつも生きた御声を聞かせてくださる。「赦しているよ」と。それによって私たちは小さな復活を繰り返し経験することができるのです。
ところで、復活したイエス様は、今どこにおられるのか。それは今、復活を覚える私たちにも重要な問いでしょう。イエス様がどこにおられるのか分からなければ、イエス様とお会いすることもできないからです。イエス様は天におられます。教会に臨在しておられます。それと同時に忘れてはならないのは、イエス様は私の内に生きておられるということです。「もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです」(ガラ220)。
イエス様は、時に失望し、弟子を止めようと決意する私たちにご自分から近づいてくださいます。ともに歩かれ、語りかけ、目と耳を開いてくださり、もう一度救いの喜びを私たちに戻し、主に仕えることを喜ぶ霊で私たちを支えてくださいます。主は今も生きて語りかけてくださいます。生きた聖書のみことばをもって私たちに語りかけます。「赦しているよ」と、私たちが一番求めている、聞きたいことばを聞かせてくださいます。天において、教会で、そして私たちのうちで。そして私たちはそこから立ち上がり、そこから再び歩み出して行くのです。私たちはイースターを覚える今朝もまた、イエス・キリストを信じ、イエス様の復活に与り、罪の赦しによって力と勇気をいただき、立ち上がり、そしてイエス様とともに出て行くのです。そして何度でもイエス様の復活に与ることのできる幸いな者として、また終わりの日には必ず復活が約束されている者として、その幸いに、恵みに感謝し喜びながら、よみがえられ、今も生きておられる主とともに、これからも歩んでまいりましょう。