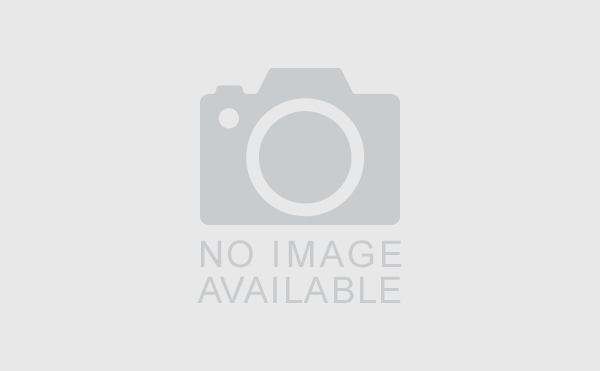2025年8月3日 主日礼拝「神の栄光が現されるところ」
賛 美
前奏(黙祷)
招 詞 詩篇146篇1〜7節
讃 美 讃美歌14「わがたまさめて」
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 讃美歌68「父なる御神に」
聖書朗読 コリント人への手紙第一 11章2〜16節
説 教 「神の栄光が現されるところ」
讃 美 讃美歌529「ああうれし、わが身も」
聖餐式 信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
讃 美 讃美歌205「わが主よ、今ここにて」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 コリント人への手紙第一 10章31節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
コリント人への手紙第一 11章2〜16節
説教題
「神の栄光が現されるところ」
今週の聖句
こういうわけで、あなたがたは、食べるにも飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を現すためにしなさい。
コリント人への手紙第一 10章31節
説教「神の栄光が現されるところ」
コリント人への手紙第一11章2〜16節
はじめに——この世(時代)の常識について
皆さんはこの世(この時代)の常識、いわゆる「それが普通なのでは」と考えることについてどう思われるでしょうか。人生経験を積み重ね、成熟し落ち着いた立派な大人には、この常識や普通というものは非常に良いものとして捉えられるのかもしれませんが、時にこの常識や普通というものは馬鹿にされ敬遠されがちなのかもしれません。表面上は敬う態度を見せつつも、実際には関わりを避けたり、嫌って避けたりしがち。普通と違うことをするのを好み、またそれが人からの称賛を得たり、羨望の眼差しが向けられたりするのではないかと考える。特にエネルギーに満ち溢れ、自分の力に自信がある若い頃などは、常識や普通、ルールと言われるものに対して反発し、そこから自由になり、自分の力、栄光を誇りたがるものなのかもしれません。それはある意味においては、それまでの常識や普通の枠を越えて新しい芸術やファッションなどの文化を創造してきたり、新しい技術を開発してきたりという良い面もあるでしょう。何よりもイエス様は、人の間で間違って確立して来てしまっていた常識や普通を、群衆に語られたみことばと教えによってひっくり返し、また2度ほど机をひっくり返しましたが、本来の神が「良し」とされた自然な常識や普通へと軌道修正されました。それはイエス様だからこそできたことです。イエス様のように、エネルギーが真に正しい知恵によって良い方向に用いられるならば、「若いって素晴らしい」という称賛が得られることもあるでしょう。しかし、その素晴らしい若さ、エネルギーを間違った方向に用いがちなのが人間の愚かしさです。常識やルールを馬鹿にし、それらから外れたことをすることによって自分の力、自由、栄光を世にアピールするような。しかし、それを見ても恐らく大抵の世の人々は、本当には「凄いな、素晴らしいな、憧れる」とは思わないものなのではないでしょうか。かえって羨望の眼差しとは違う、白い目で見られてしまうかもしれません。ちなみに飛び抜けて優秀な人というのは、一周回って「できない人」に見えるのだそうです。パウロもそうでしたね。
コリント人への手紙が書かれた当時のコリントの教会も、言わば若くて成長途上の教会でした。教会全体には神の恵みによって罪の奴隷から解放され、自由の身とされた喜びが満ち溢れ、また若いエネルギーに満ち溢れていたことでしょう。そこでパウロは前回のところでコリントの教会にこのように命じました。「こういうわけで、あなたがたは、食べるにも飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を現すためにしなさい。ユダヤ人にも、ギリシア人にも、神の教会にも、つまずきを与えない者になりなさい。私も、人々が救われるために、自分の利益ではなく多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせよう(受け入れよう、受け入れてもらおう)と努めているのです。私がキリストに倣う者であるように、あなたがたも私に倣う者でありなさい」(1031-111)。それに続いての今日の箇所です。
今日の箇所の最初に、パウロはコリントの教会を褒めています。それはすべての点でパウロを覚え、パウロから受けた教えを堅く守っていることを褒めています。しかし限られた時間の中での説教、遠く離れたところからの手紙などですべてを教えきることは、いくらパウロであってもそうできるものではありません。教会が成長し自立して行く中で、どうしてもパウロが教えていない部分で若干の、しかし重大なズレが生じてしまっていました。この手紙の冒頭では、パウロは彼のもとにコリント教会からの質問状を届けに来たクロエという人の口から、教会内に対立があることを聞かされました(Ⅰコリ111)。また、パウロの耳には「ちょっと聞いてよ、コリントの教会ではこんなひどいことが平気で行われているらしいよ」という噂が、あちらこちらから聞こえて来ていました(Ⅰコリ51)。そしてそれは本当のことだったのです。
パウロはこれまで手紙の中で、「神にある自由」「キリスト者の自由」について語ってきました。そして今日の箇所もその話しの流れの中で語られているところです。
ところで、今の時代、今日の箇所を1節ずつ丁寧にそのまま語ったらどうなるでしょうか。相当な反発や疑問が予想されます。それは今の私たちの文化とは相当異なる当時の文化、常識、普通の中で語られているからです。だからと言って私たちとは関係ないと読み飛ばしてはいけません。聖書の神のみことばは生きて働かれるからです。今日の箇所も、今の時代を生きる私たちにとても大切なことが語られているところです。
頭のかぶり物
11章3節 しかし、あなたがたに次のことを知ってほしいのです。すべての男のかしらはキリストであり、女のかしらは男であり、キリストのかしらは神です。
11章4節 男はだれでも祈りや預言をするとき、頭をおおっていたら、自分の頭を辱めることになります。
3節から展開されるパウロの教えを理解するには「かしら」を用いたパウロの言葉遊びのようなものがあることを知る必要があります。3節では「かしら」と訳されているギリシャ語(κεφαλὴ)ですが、これは不思議にも日本語の意味にもまったく共通しており、「頭、髪の毛、そして親分(主、主人)」といった意味を持つ語です。
パウロはコリントの教会で行われていた「自由な行動」の1つの例として「かぶりもの」を取り上げます。このかぶり物において、コリントの教会では自由な行いがあったのです。この「かぶり物(κατακαλύπτω)」というギリシャ語ですが、これは「顔を覆うベール、顔にはかからないように頭の上にかぶった布」、そして14・15節にある「垂らした長い髪」をあらわす語です。
4節でまず男性のかぶり物について取り上げます。今の時代、男性が帽子などのかぶり物を被ったり、長髪で街を歩いたりするということは全然おかしいことではありませんが、当時はとても奇妙なファッションでした。頭にかぶり物(顔を覆うベール、頭の上に布)をかぶったり長髪で街を歩いたりしようものなら、白い目で見られたのです。そしてコリントの教会の男性信徒の中に、この当時では奇妙なファッションをして礼拝に出席し、街を歩いていた人が結構いたようです。教会の中で流行したのでしょうか。変わった格好、前衛的な(既存の枠を越えようとする)ファッションで「俺はこんなにも自由だ!何をしても赦される!こんなにも喜んでいるんだ!救われるってこんなにも素晴らしい!」とアピールしたのでしょうか。それは神の栄光ではなく、世に対する自分の栄光、優位性のようなもののアピールだったのではないでしょうか。
私自身にも覚えがありますが、そのような時というのは、自分の弱さとか足りなさとか、コンプレックスとかを隠したりごまかしたり、変に周囲の人に自分の力とか優位性をアピールする時なのではないでしょうか。もしその姿をもって目の前の誰かのために祈ったり、神のみことばを伝え証したりしても、果たしてそれは本当に神の栄光を現すことになるのかどうか、考えさせられるところです。
本当に神を信じ、罪の赦しを信じ、自由の身とされ、神の御前に進み出る者の本当の姿というのは、いたって普通に、いや普通以下の「できない人」のようにでしょうか。自分の弱さとか足りなさとかを包み隠さずに、神の御前で砕かれた魂、砕かれ悔いた心を注ぎ出すのです。弱さをさらけ出して涙を流し、すべてをご存知で、すべてを赦すことのできる全知全能なる神を心から信頼し、寄りすがり、そしてひれ伏すようにして求め祈る姿。自分のためばかりではない、目の前にいる誰かの罪をも自分のことのように悲しみ、その赦しのためにもひれ伏して祈る姿は、果たして周囲の人々に弱さを感じさせるものとなるのでしょうか。神の力のなさを感じさせるものとなるのでしょうか。かえって信仰によるその人の強さ、神の強さ偉大さを感じさせるのではないでしょうか。そこに神の栄光が現されるのです。そしてそのような信仰、そのような礼拝を神は喜んで受け入れてくださるのです。そのような所に神の偉大なみわざが現されるのです。そこに赦しがあり、そこに大きな神の祝福が注がれるのです。
それなのに、例えば当時の男性が頭にかぶり物を被り、既存の枠を越えようとする変わった格好をして自由や力を変にアピールし、自分を覆い、自分を隠しごまかすならば、「自分の頭を辱めることになる」とパウロは言います。頭というのはその人を代表する体の部分です。「かしら」です。私たちの「かしら」、教会の「かしら」「親分」「主、主人」は誰でしょうか。キリストです。そのイエス・キリストの名は今や全地に知れ渡っています。そのイエス・キリストの名をかえって辱めることになってしまう。イエス・キリストの名声を傷つけ汚すことになってしまう。それは神のみならず、教会のみならず、これから救われるべき世の人々にとっても大損害です。
5節からは同じように、教会のかしらであるキリストを辱める行為として、女性の頭のかぶり物について述べます。
当時のこの地域の常識では、女性が髪を人に見せることを、「男性の性欲を刺激する恥ずべき行為」と考えられていました。結婚した女性が頭にかぶり物をつけないことは、自分を男たちと性的関係を結ぶ意思のある人(売春婦)と見なして欲しいと示すのと同じ行いでした。しかし、偶像の神殿の女司祭や遊女が自分のヘアスタイルを自慢するようになり、それがギリシア・ローマの上流層の経済的にも、立場的にも恵まれた女性の間でも流行するようになりました。そのような影響がコリントの教会の女性信徒の間に入り込んできたようです。彼女たちはそのような格好で礼拝に出席し、また街を歩いていました。「私たちはすべての罪が赦されて、自由の身とされている」そのことを、自由な格好をするという形で証明しようとしたのでしょう。しかし世の人々から見るならば、その姿は世の性的に乱れた女性と同じでした。
11章5節 しかし、女はだれでも祈りや預言をするとき、頭にかぶり物を着けていなかったら、自分の頭を辱めることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのです。
注目したいのは、パウロは当時社会的地位があまり認められていなかった女性にも、祈りや預言といった重要な働きを認めて任せているというところです。また創世記では「人がひとりでいるのは良くない。わたしは人のために、ふさわしい助け手を造ろう」と、男から女を創造されたことが記されています。すでに知られていることですが、この「助け手」というのは、お互いの違いを認識して受け入れ合い、尊重し、互いを必要とする同等な関係です。ですから聖書は一貫して、またここからも決して女性を侮ったり軽んじたりすることを教えてはいません。女性が侮られ軽んじられるという世の常識から解放されたその自由を、間違った方法で証明する必要はないことを教えているのです。「かぶり物を付けないなら、自分の頭、かしらを辱めることになる」。これは男性に向けて語られたことと同じ事です。それは神の栄光を現すどころか、恥ずかしいことですよと教えるのです。そして神の恵みによって自由の身とされたあなたがたであるなら、それを避けるようにと教えるのです。
神の創造された秩序の中で
7節からパウロは、頭のかぶりものについてから、さらに神の創造された秩序に素直に服従するようにと教えます。
創世記に記されている神による世界の創造のみわざ。この世界のすべて、天と天と地に満ちているもの、自然、すべては、神がまったくの無から創造されたものです。そして神は1つ1つそれらを造られ、1つ1つそれらを見て「良し」と見られました。満足されたのです。神が満足されたこと、それが正解、それが最も善く、1つも間違っていない、エラーがない、乱れがないということです。その世界は本当に素晴らしいのです。美しいのです。
この「良し」というのは、ヘブル語で「טוֹב(トーヴ)」です。この「טוֹב(トーヴ)」は聖書のあちらこちらに見られます。その所々において「良い」「幸福」「好ましい」「美しい」「かわいい」「善」「慈しみ」「素晴らしさ」と訳される語です。
ある先生は、「神ははじめに万物を創造されたが、それは秩序を創造されたことでもある」と言われました。その通りです。神は世界のすべてを創造され、秩序を創造され、その中に人を住まわせました。そして神は世界とそのすべてをご自身のご支配のもとに置かれました。支配と言っても恐ろしい支配ではありません。慈しみによってです。それが良いとして、それが好ましい、美しいとしてです。御心にかなっている。それが人にとって本当の幸福であるのです。はじめに神の創造された無垢で善な秩序、そして無垢で善な支配(支えと配慮に満ちた世界)の中に生きてこそ、人は本当に幸福であり、自由なのです。その素晴らしく美しく整った世界に、神の栄光が現されるのです。
神の民の歴史を見てみましょう。エジプトでのこの世の王ファラオと偶像礼拝の悪い支配から神のあわれみと恵み、そして偉大なみわざによって解放され、自由の身とされた神の民はどうだったでしょうか。神のご支配(良い支配、支えと配慮)のもとに置かれたではありませんか。そして神の支えとご配慮の中、約束の地を目指して旅を続けたのです。自由の身とされましたが、彼らはてんでんばらばらに約束の地を目指したのではなく、神の箱、神の臨在を中心にして、神が命じられた通り、部族ごとに美しく整列し、美しく約束の地へと向かって前進しました。その旅の途中、神は栄光をもって民を守り、導き、養われました。しかし神の民は、神が立てられた指導者モーセとアロンに逆らい、つまり神が立てられた秩序に逆らった者たちは罰を受けて滅ぼされてしまいました。彼らは恵みによって与えられた自由を間違ってしまったのです。しかし残された者たちが変わらずに神の箱、神の臨在を中心にして、神が命じられた通り、部族ごとに整列し、約束の地へと向かって前進するその整えられた美しい隊列を見て、バラクという王に神の民を呪うように雇われたバラムという占い師は、民を呪うどころか、思わず3回も神の民を祝福してしまいました。思わず神を褒め称えてしまいました。そこに神の素晴らしい栄光を見たからです。
また、ソロモン王の名声を聞いたシェバの女王は、大勢の従者を率いてエルサレムのソロモンのところにやって来ました。シェバの女王は、ソロモンが建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、給仕たちの態度とその服装、献酌官たち、そしてソロモンが主の宮で献げた全焼のささげ物を見て、息も止まるばかりに驚いてしまいました。そして神を褒め称えたのです。「なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは。なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことができる、このあなたの家来たちは。あなたの神、主がほめたたえられますように。主はあなたを喜び、イスラエルの王座にあなたを就かせられました。主はイスラエルをとこしえに愛しておられるので、あなたを王とし、公正と正義を行わせるのです」(Ⅰ列108-9)。
先週も考えましたが、神の栄光とは何でしょうか。「栄光」というヘブル語の元々の意味は「非常に重いもの」です。それを目の前にしたら、思わず押しつぶされそうになり、思わず膝が折られてひれ伏してしまうもの。それが神の栄光というものです。また「神の臨在」でもあるでしょう。真の神がここにおられる。そう感じる時、人は恐れを感じ、膝から崩れ落ちるようにしてひれ伏すのではないでしょうか。
そしてキリストは、ある夜、「神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を空しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられ」ました。その時、神の栄光が現れ、天に御使いたちとともにおびただしい数の天の軍勢が現れ「いと高き所で、神に栄光あれ」と神を賛美しました。羊飼いたちは恐れてひれ伏しました。そして飼い葉桶に寝ておられたイエス様に神の栄光を見て、思わずひれ伏したのです。
神であるイエス・キリストが人としての姿をもって人々の前に現れ、自らを低くして、貧しい者、弱い者たちに寄り添い、生きられることによって、神の栄光が現されました。多くの群衆、病人、貧しい人、罪人がイエス様の前にひれ伏しました。神であるイエス・キリストが、人の罪を背負い、十字架につけられ、苦しまれ、死んで葬られ、そして3日目によみがえられることによって神の栄光が現されました。その神の栄光の現れであるイエス・キリストを信じる信仰によって、1人の罪人の罪が赦され、自由にされ、救われる。そこに神の栄光が現されるのです。そこに神の臨在があるのです。その前に人は神を恐れ、感謝してひれ伏すのです。
以前、まだ私たちが真の神を知らない罪人であった時、その罪の支配に苦しみ、そこからの解放を願い、真の神、真の救いを求めてキリストの教会を訪れた時、何をご覧になって「ここに真の神がおられる。ここにまことの救いがある」と感じたのでしょうか。罪赦され、自由とされた者がその自由を謳歌して、何をしても赦されるという思いからの自由奔放な行動、自由でめちゃくちゃな整えられていない礼拝、遅刻も平気、服装も自由、自由に争い、自由に赦し合うこともなく、一致のない姿。玄関のスリッパなんかバラバラ、庭の草はボウボウ。ご婦人がご主人のことなどまるで気にすることもなく、自由奔放に神を礼拝している。それを見て「すべての罪が赦された者はこんなにも自由なのだ。自由って素晴らしい!私も救われたい!」そう思われたのでしょうか。そうではないでしょう。そうだったとしたら、ここに集まっている私たちはただのならず者の集団です。そこに皆が神を恐れ、神を愛し、神を喜ぶ姿があった。神に愛され神に赦されているからこそ神と教会を愛し、神と教会に仕え、家族や隣人を愛し、家族や隣人に仕えている姿があった。礼拝とか賛美においても、その形は自由であっても、そこに整えられた秩序、善、美しさを見て、自然と、本能的に神の栄光、神の臨在、神の救い、神の素晴らしさをそこに見て、感じ、「私も救われたい!」そう思われたのではないでしょうか。
私も1999年5月の特別伝道集会で初めてこの教会を訪ねた時、そこに聖なるものを感じました。静まった礼拝堂、そこに美しく響くバイオリンが奏でる讃美歌。揃えられたスリッパ。きちんと座って静かに始まりを待つ方々。皆が神を恐れ、神を愛し、神を喜び神に仕える姿。前のめりで神のみことばが語られること、また救われて欲しいとそこに招いておられる方の救いを神に期待し、みことばを待っている姿。そこに「ここに神がおられるのだ」と神の臨在、そして神の聖さを感じたのです。今考えると、思わずひれ伏してしまいそうな聖霊の充満、神の愛、親心の充満、重みを感じたのです。つまりそこに神の栄光が現されていたのです。そして見事に私は福音を信じ、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに寄りすがり救われてしまいました。そこに神の栄光が現されたのです。
皆さんの場合、クリスチャンに対する印象はどのようなものだったでしょうか。また初めの頃の教会、または礼拝の印象はどのようなものだったでしょうか。もちろん難しくて良く分からなかったということはあったでしょう。それは別にして、何に神の栄光を感じたでしょうか。礼拝や賛美の形式は色々でしょうが、そこにはやはり自由奔放ではない、整えられた秩序があったのではないでしょうか。自分の栄光を現そうとするのではなく、神の栄光を現そうとする礼拝、賛美があったのではないでしょうか。そしてそれらは自然に、本能的に分かるのです。
私たちは世の常識とか、秩序とか、それらは自由とは相反するもののように考えてしまうところがあるのかもしれません。世の常識とか、秩序とか、それらを馬鹿にしてしまう性質があるのかもしれません。しかし自由にされたからと言って、そのようなものを軽く見たり、無視してしまうような所に、世の人々は決して神の栄光、神の救いを見ることはないでしょう。間違った自由アピールをしてみても、人はそこに神の栄光を感じることはないのです。私自身、耳に7つのピアスの穴があいていますが、牧師が自由だからと言ってピアス7個つけてみても、多分相手は神の栄光をそこに見ることはないだろうと判断して、付けていません。まぁそれは13節でパウロが言っているとおり、それぞれの立場で自分で考えて判断するべきことです。そうすることによって神の栄光が現されると考えるならばすれば良いし、そうでなければしなくて良いのです。
人は皆、神によって神のかたちに似せて造られた者です。ですから神が造られた自然、立てられた秩序、神との平和な関係、神による幸いな支配、支えと配慮の中に生きることを深い所で求める者たちです。飢え渇きがあるのです。この世は自由の謳歌こそ素晴らしいとされる世ですが、神に造られた人は皆、この世とは違うものを求めているのです。聖さを求めているのです。聖さというのは、神のものとして特別にこの世から取り分けられたもののことです。教会です。教会の礼拝です。神の国です。天の御国です。私たち教会は、この世のまだ真の神と、真の救い、真の自由、本来の神が創造された良い自然、普通、世界に生きることの素晴らしさを知らない人々に、それらを証して行く者たちです。教会の姿と神への礼拝を通してです。イエス・キリストの十字架による救いの恵み、罪赦され、自由にされた者として、自由でありながらも信仰の本質、中心は決して譲ることなく、私たちの整えられた美しさ、素晴らしさを通して神の栄光を現して行くのです。そして世の人々は、そのような私たちの内にこそ神の栄光を見いだし、真の自由、救いを求め、救われる魂が起こされて行くでしょう。私たちは人々が救われ、神の栄光が現されるために、自分の利益ではなく多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせる。そのような主イエス・キリストに倣う者でありたいと願います。そしてそこにこそ神の栄光が現れ、そこにこそ私たち自身の真の自由、真の喜び、幸福があるのです。
今一度、パウロの言葉に聞きましょう。
「こういうわけで、あなたがたは、食べるにも飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を現すためにしなさい。ユダヤ人にも、ギリシア人にも、神の教会にも、つまずきを与えない者になりなさい。私も、人々が救われるために、自分の利益ではなく多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせようと努めているのです。私がキリストに倣う者であるように、あなたがたも私に倣う者でありなさい」。