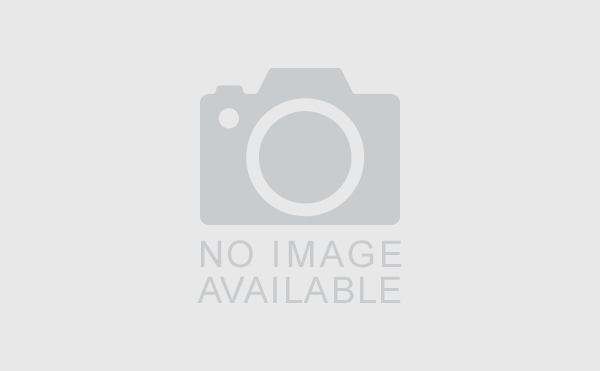2025年10月5日 主日礼拝「愛がなければ」
賛 美
前奏(黙祷)
招 詞 詩篇150篇
讃 美 讃美歌73「くすしきかみ」
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 讃美歌121「まぶねのなかに」
聖書朗読 コリント人への手紙第一 13章1〜7節
説 教 「愛がなければ」
讃 美 讃美歌332「主はいのちを」
聖餐式 信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
讃 美 讃美歌204「すくいの君なる」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 ヨハネの手紙 第一 4章8節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
コリント人への手紙第一 13章1〜7節
説教題
「愛がなければ」
今週の聖句
愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。
ヨハネの手紙 第一 4章8節
説教「愛がなければ」
コリント人への手紙第一 13章1〜7節
はるかにまさる道を示しましょう——
10月に入りましたが、先月の9月は第一コリント12章を通してのみことばに聞いてまいりました。私たちにはそれぞれ皆違った様々な賜物が与えられていること。そして前回は、その賜物というのはギリシャ語で「カリスマ」であり、それは「カリス(恵み)」の受け身形だということを見ました。賜物は本当に良いものを与えたいと心から願われる父である神の御霊(親心)に基づいて与えられた恵み(無償の非常に良い贈り物)であり、実はそれは知らず知らずのうちに受けている恩恵です。コリントの教会では、皆が救われた喜びの中、神を愛し、教会を愛し、神のために、教会のために自分が出来ることを喜んでして行くうちに、「自分にはこんな賜物があったのか。あの人にはこんな賜物があったのか」のように、段々とそれぞれの賜物が表に現れてきたのでした。そして「カリス(恵み)」には「理由」と訳せる活用法もあり、現代のギリシャ語になると「古代の戦車の二重の車輪(重ね重ね)」という意味もあるということでしたね。神から恵みによって知らず知らずのうちに受けている恩恵には、神の重ね重ねの、幾重にも重ねられた「さらにさらに」という理由や目的があるのです。それが私たち全員に、それぞれに必ず与えられているのです。私たちは偶然の産物ではなく、父なる神が丁寧に造られた神の作品ですから、当然作者である父なる神の意図、親心(御霊)による理由や目的が何重にも込められているのです。しかし、当時コリントという大都市においては、自分を誇ってアピールするという文化が色濃くありました。そこに住む人々は自然とできるだけ際立つ派手な賜物を求めていました。そして派手な賜物を持っている人を尊び、そうでない人を軽んじていました。派手な賜物を持っている人は尊敬され、礼儀が尽くされ、そうでない人は蔑まれ、礼儀に反することをされていました。そのような世の影響がコリントの教会の中にも入り込み、派手な賜物(第1位は異言)を持つ人や、裕福な一部の人たちが教会の中で幅をきかせ、そうでない人は端に追いやられていました。そしてお互いの間に分裂や対立があり、救われた喜びに満ち、皆が生き生きしていたはずの教会が、「あなたがたの中に病人(元気がない人、調子の悪い日と)や死人(まるで死んでしまっているような人)がたくさんいる」状態に陥ってしまっていたのです。そのようなコリントの聖徒たちに、パウロはキリストのからだである教会を人の体にたとえて「あなたがたそれぞれの賜物(できること、得意なこと)は神からのものであり、どれも重要で、かえって取るに足らない、他より弱く見える部分が、かえってなくてはならないのだ」と神の御心を語りました。そして最後に「あなたがたは、よりすぐれた賜物を熱心に求めなさい」と勧めました。より優れた賜物というのは、相手の徳を高める賜物のことです。皆の益となるという面から見ての賜物のことです。際だって目立つ賜物を欲しがるのではなく、与えられている賜物に感謝しつつ、その賜物で神のために、教会のためにさらに何ができるかを求めることです。そのためにパウロは「私は今、はるかにまさる道を示しましょう」と言い、今日の13章に入って行くのです。
13章は全体が美しい詩の形式をとっている「愛の賛歌」としてとても有名です。その愛の賛歌を通して、それぞれの賜物をより優れたものにするのは愛であるとパウロは教えます。
ところで、13章の「愛の賛歌」、特に4節以降は結婚式でたびたび引用されるところです。どうして教会に対する勧めが結婚式で引用されるのでしょうか。ほとんどの人間が憧れる理想的な愛の形があるからでしょうか。それもそうかもしれませんが、聖書の他の箇所では、神はご自身と私たちとの関係、神と教会との関係を「ちょうど、ぴったり同じように」として結婚にたとえておられます。結婚というのは、頭の中がお花畑だけではなく、重要で厳粛で厳守すべき契約です。お互いが選び取り、お互いが愛することを堅く心で決め、そして死が二人を分かつまで約束を守り通すことを約束することでもあります。神と私たちとの間で、神はすでに約束済み。真実な神は決して契約を破ることはなさいません。しかし、私たちの方は契約を破ってしまう危険や弱さがいつも隣り合わせでしょう。ですからその危険を回避するために、私たちはどうしても神の偉大な愛を知り、いや知らされ、それを強く心に覚えておく必要があるのです。
愛のない異言の賜物
13章1節 たとえ私が人の異言や御使いの異言で話しても、愛がなければ、騒がしいどらや、うるさいシンバルと同じです。
御霊の賜物の中で最初に出て来るのは、コリント教会で多くの人々から偏って重んじられていた異言です。異言とは本来ならば素晴らしい賜物です。コリントの教会は、異言を語る時には「御使いの異言」を語っていると信じていました。「異言」というギリシャ語は「舌」という意味で、つまり異言は御使いの舌が語っているのだということです。御使いは神からのメッセンジャー(伝令者)です。異言というのは御使いが神からのメッセージを直接語っている言葉をそのまま語るものです。それは異言を語っている人の言葉を聞く限り、人間の言葉、地上の言葉ではないのでしょう。そのような特別な賜物を持つ人は高慢になり、愛のないまま、自分の利益のために用いて強調していました。兄弟姉妹への愛と配慮を失ってしまっていたのです。
「騒がしいどら」というのは、直訳すると「騒がしい青銅」です。当時コリントにもあったギリシャの劇場で拡声器として使用されていた、音を大きくするために考案された青銅の音響装置のことです。「シンバル」というのは、金属で作られた薄くて丸い皿のような楽器で、ぶつけて音を出すように考案されたものです。これはローマの神殿、異教の宗教行事で女司祭が儀式で用いたもので、無我(恍惚)状態に至らせるものとしてよく使用されていました。そして「うるさい」と形容詞が付いていますが、これは本来金属音を意味する語ですが、使われる場面によっては周囲の不快感や混乱を表現する目的で使われます。先ほども申しました通り、パウロは決して異言を悪いこととは言っていません。本来は素晴らしい賜物です。しかし愛を失ってしまっては、異言は意味不明であり、ただの自己アピールであり、耳ざわりなだけであると同時に、せっかくの素晴らしい賜物も、教会にとって、兄弟姉妹にとって空しいだけ、何の役にも立たないものであるとパウロは言います。同じようにどのような賜物であっても、愛を失い、相手を大切にする思い、相手に対する関心や配慮を失ってしまい、ただの自己アピールのようなものであったりするならば、どれもこれも空しい、何の役にも立たない。例えば誰かに優しい励ましの言葉、あるいは必要な注意を与えるなら(それらが出来るというのも賜物でしょう)、拡声器を使って周囲にも聞かせるのではなく、そっと優しく耳元で話せば良いのでしょう。スリッパを揃える(小さなことに気付き、実行できるのも賜物でしょう)時も、一生懸命やっていますアピールをしなくても良いのです。そうでなければ、ただの「騒がしいどらや、うるさいシンバル」なのです。
愛のない預言と知識と信仰
13章2節 たとえ私が預言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、私は無に等しいのです。
「たとえ私が」と言います。つまり「たとえ私、パウロが」ということです。パウロは確かにこれらの賜物を持っていました。「預言の賜物」、それは過去の出来事を聖書の中などから調べ、そこから未来の出来事を見通して、御霊の導きのもとで神のメッセージを伝える力を指します。
「奥義」とはまだ知られていないこと。パウロは復活のイエス様によって召された直後の荒野での経験、第3の天に引き上げられた経験、復活のイエス様から直接知らされたことによって、恐らく人にはまだ知られていない「奥義」に通じていたのでしょう。しかしそのような素晴らしい経験を生涯自慢するようにして自ら進んで語るようなことはしませんでした。自己アピール、自分の権威を知らしめるためには用いなかったのです。
「知識」はすでに知られていること。聖書のみことばによるのでしょう。パウロは信仰のエリートとしてガマリエルのもとで深く学んだ人です。聖書も丸暗記するほどに知識に満ちていました。
パウロはこれら賜物をもってパウロ書簡を書き、それが聖書として皆の益のために用いられているのです。
「山をも動かす信仰」というのは、イエス・キリストを救い主として信じる信仰と言うよりは、熱狂的に、強烈に、そして楽観的な態度を固く持ちつつ、周りの人々を励ます賜物です。私たちの周りにもそのような賜物を持つ方がおられます。こちらが引いてしまうくらい熱狂的に、強烈に、そして楽観的な態度でごりごり来られる方が。それもまた本来素晴らしい賜物です。私にはないものですから憧れます。
しかし、これらの賜物も、愛がないなら「無に等しい、nothig I am、皆無、空虚、むなしい、何の役にも立たない」のだと言うのです。パウロは「愛がないなら、『私は』無に等しいのです」と言っているのです。ここにどこか、このパウロをしても自分の愛のなさに対する失望のようなものを感じないでしょうか。高慢のかけらもありません。
同じように「私」を用いて続けます。
愛のない施しと献身
13章3節 たとえ私が持っている物のすべてを分け与えても、たとえ私のからだを引き渡して誇ることになっても、愛がなければ、何の役にも立ちません。
新改訳聖書の欄外にも記されていると思いますが、別の訳では「誇るために私のからだを引き渡しても」。また異本では「私のからだを焼かれるために引き渡しても」となっています。私が持っている物のすべてを分け与えても。これは施しの賜物のことです。持っているものを惜しみなく施すことができるのも賜物なのです。そして私のからだを引き渡す、焼かれるために引き渡す。つまり全焼のささげ物として神に引き渡したとしても。これは献身の賜物のことです。献身(と言っても、牧師や宣教師になろうというものだけではありません。この身と霊、賜物を神のために献げますというもの)しようという思いもまた神からの賜物なのです。しかし同じように、そこに愛がないならば何の役にも立ちません。
世の中には善い行いや人道的な活動のために身を投じる人々がいます。しかしパウロが語っている愛は、イエス・キリストを通して人間にはっきりと示された神の愛のことです。先ほど「この人を見よ」と賛美した、イエス・キリストに見る神の愛のことです。この愛は、イエス・キリストを信じることなしには本当には知ることができません。そしてこの愛は、この世にはない完全な愛です。この愛なしに、それがどんなに良いことだとしても、それがたとえ献身することだとしても、自分なりの生きがいややりがい、価値観のために払う犠牲であるならばそれは自己中心であり、自分を誇ることです。また「自分はこんなにも犠牲を払っているのに」といったような、神に対する恨みや憎しみさえ心の中に隠し持ってしまうことにもなり得るのです。そのような施し、献身ならば何の役にも立ちません。自分のためにも、他人のためにも、教会のためにもなりません。ですから神のまことの愛なしに、自分中心になって賜物を用いてしまうことに警戒しなければなりません。神の愛によって賜物を用いていくことを常に心掛けなければなりません。そのためにも、イエス・キリストを心から信じ、「この人を見よ」と、イエス・キリストを通して示された神の愛を知ることです。
愛の性質、特長——肯定文による
ここからは、ここに登場する言葉の意味を中心に見て行きたいと思います。よろしければ簡単にメモなど取りながらお聞きいただければと思います。そして最後に、皆さんに重要な問いかけをさせていただきます。
13章4a節 愛は寛容であり、愛は親切です。
「寛容・μακροθυμεῖ」とは、辛抱強い、辛抱強く耐えること。そして「親切・χρηστεύεται」とは、相手の身になって、その人の為に何かをすること。思いやりを持って人のために尽くすことです。
愛の性質、特長——否定文による
13章4b節 愛は人をねたみません。愛は自慢せず、高慢になりません。
13章5節 礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、
13章6節 不正を喜ばずに、真理を喜びます。
パウロは否定文を用いて、愛があるなら行わない8つのことを挙げます。
「ねたむ・ζηλοῖ」は嫉妬すること。自分より優れている人をうらやんでねたむこと。聖書は「人を自分よりすぐれた者と思いなさい」と言います(ピリ23)。まことの愛のお方であるイエス様は、まさにそれを実践された方です。ご自分は神であられるのに、罪人、病人、貧しく弱い人を尊重し、愛してくださいました。
「自慢する・περπερεύεται」は法螺(法螺貝)吹きのこと。大げさに言い、でたらめを言うことです。そして「高慢になる・φυσιοῦται」は、誇る、鼻息が荒い、横柄、遠慮がないということ。
「礼儀に反することをする」は失礼な態度を取るということでしょう。
「自分の利益を求めない」、つまり自分を無にして相手の利益を求めること。
「苛立たない」という語の中には、怒らないという意味も込められています。
「人がした悪を心に留めず」の「留める・λογίζεται」というのは、もともと会計係の使う言葉です。ある事項を忘れないために帳簿に記入すること。つまり、他人が自分にした色々な事を恨んで、それを記録に留めて後生大事に保存することです。しかし本当の愛はそのようなことをしないのです。真実の愛というのは、赦すことができないことを赦すことでもあります。まさに神の愛でしょう。
「不正を喜ばず」は、自分が行う悪事を喜ばないという意味であると同時に、誰か他の人が悪口を言われたり、罪を犯したり、不正に取り扱われているのを見て良い気分にならないことでもあります。
この4〜6節の「〜しない」という形で愛の性質、特長を語る箇所は、コリントの教会の愛のなさを反省させる文でもあります。コリント人への手紙の最初から振り返っていただくとお分かりと思いますが、コリント教会の分争(33以下)、知識についての誇り(318以下)、救いの完成を得ているとの自負心(47以下)、女性の身だしなみの廃棄(112以下)、愛餐会での利己的行動(1117以下)、訴訟好き(61以下)等は、ねたみ、自慢、非礼、利己心、怒り、人の悪の追求など、愛のなさ、愛の欠如が表に現れてきたことによって起こった問題でした。この箇所をパウロが意図的に当てこすったわけではないでしょうけれども、コリント教会の問題の多くが愛の欠如によるものであったことが分かるのではないでしょうか。
愛の性質、特長——総括
最後に愛の性質、特長を総まとめしてこのように述べます。
13章7節 すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。
「すべて」と4回繰り返されていますが、すべてとは1節から語られたことすべてにおいてです。「すべてを耐える」は、すべてを覆うとも訳せます。そうです。愛はすべてを覆うのです。また「すべてを忍ぶ」とは、どんなことにも踏みとどまるということ。愛はすべてにおいて私たちを踏みとどまらせるのです。しかし、何でも耐えて、何でも我慢して、何でも信じて、何でも望んで、何でも忍ぶわけではありません。やはりそれらもイエス・キリストを通して示される神の愛によらなければ、何の役にも立たないのです。
自分の愛のなさ、神の愛の偉大さを知る
今日の説教はこれで終わります。
ここで皆さんにして欲しい作業があります。それは、今日の箇所の4〜7節の一部分を変えて読んでみていただくことです。すでにされたことがある方もおられるかもしれませんが、今一度、神の御前で素直にへりくだってしてみてください。
4節の頭に「愛は」とありますが、これはギリシャ語の文法的には5節の頭にも、6節の頭にも、7節の頭にも付く語です。その「愛は」というところをご自分の名前に置き換えて読んでみてください。
いかがでしょうか。自分は本当にまことの愛からいかに遠い人間であるかが思い知らされるのではないでしょうか。私などは自分に失望し、また絶望さえしてしまいます。しかし同時に、こんな私を主は愛してくださった、また愛してくださっているのだということにも気づかされるのではないでしょうか。
では、今度は「愛は」のところを「イエス・キリスト」に置き換えて読んでみてください。
いかがでしょうか。私たちはイエス・キリストこそが愛の人であり、神の愛を実践された方であるという事実に、改めて気づかされ、涙が出る思いがするのではないでしょうか。まことにキリストの愛がどんなものであるかが、はっきりと見えてくるのです。
神または他人が自分にした色々な事を恨んで、それを後生大事に保存してしまうような愛のない私。すぐに怒り、責め、神に対しても、人に対しても失礼な態度をとってしまう私。時には相手の不幸を願ってしまうような、愛のない最悪な私。しかしイエス・キリストの愛は、私の罪を帳消しにし、愛によってもう思い出されることはなさらないのです。愛されるに値しない私を愛される、その愛によって私たちは愛され、そして今も日々生かされているのです。私たちが罪を犯したり、過ちを犯したりするのをご覧になるなら、ご自身のことのように悲しまれ、苦しまれ、日々山のように失敗してしまう私のために、イエス・キリストは今も生きておられ、変わらない愛をもって、ご自分の十字架を示し、釘跡の残る手を上げて父なる神にとりなし祈ってくださっているのです。私たちは「この人を見よ!」と言われる方を日々仰ぐのです。
そして愛というのは、信仰によって自分の意志を働かせて相手を愛するのだという決心や努力も含んでいることを忘れてはなりません。イエス・キリストはまさに命をかけて私たちを信じ、愛そうと決心され、そして愛してくださっているのです。
「イエス・キリストは寛容であり、イエス・キリストは親切です。イエス・キリストは人をねたみません。イエス・キリストは自慢せず、高慢になりません。イエス・キリストは礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。イエス・キリストはすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍ばれます」。この私のために。
主の御姿を思い浮かべるならば、私たちは主を愛さずにはいられないはずです。そしてその愛で互いに愛し合わずにはいられないのではないでしょうか。今一度、「愛」を自分の名前に置き換えて読んでみてください。そして主の前に心からひざまずき、悔い改め、そして感謝し、尊敬し、主の愛によって立ち上がらせていただいて、ここからまた歩き出させていただこうではありませんか。
愛によって賜物を用いる
教会の中で与えられた賜物(教会を愛し、教会のために喜んで奉仕する中で、自分の賜物が現れてきた)は、からだの各部分のように、教会として機能するのに重要な役割を果たしますが、愛がその土台にいつもなければ、どのような賜物もその価値を失ってしまいます。教会が機能するためには、賜物、働き、役割よりもすぐれたもの、愛が重要なのです。愛は私たちが賜物を用いる上で、はるかにまさる道なのです。
パウロが語る愛は神ご自身のご性質でもあることを覚えましょう。またパウロが語っている愛は自己愛ではなく、隣人のための配慮と尊重を土台としていることを覚えましょう。そして愛とは、イエス・キリストを信じる信仰によって自分の意志を働かせて神と教会、隣人を愛するという努力をも含んでいることを覚えましょう。
私たちは今日からも、神に愛され、神を愛し、神に感謝し、神を尊敬し、そして心から身と霊とを、賜物を主と教会に愛をもって献げてまいりましょう。日々主を仰ぎ、はるかにまさる道、私たちの本当の祝福となる道をともに歩んでまいりましょう。