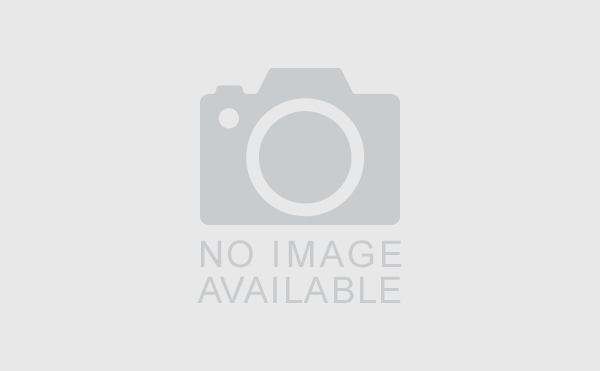2025年5月18日 主日礼拝「主よ、終わりまで仕えまつらん」
賛 美 新聖歌395「主はガリラヤ湖の」
プレイズ「明日を守られるイエス様」
前奏(黙祷)
招 詞 イザヤ書40章6〜8節
讃 美 讃美歌7「主のみいつと」
罪の告白・赦しの宣言
信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 讃美歌171「なおしばしの」
聖書朗読 コリント人への手紙第一7章25〜40節
説 教 「主よ、終わりまで仕えまつらん」
讃 美 讃美歌338「主よ、おわりまで」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 ヨハネの手紙第一2章17節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
コリント人への手紙第一7章25〜40節
説教題
「主よ、終わりまで仕えまつらん」
今週の聖句
世と、世の欲は過ぎ去ります。しかし、神のみこころを行う者は永遠に生き続けます。
ヨハネの手紙 第一 2章17節
説教「主よ、終わりまで仕えまつらん」
コリント人への手紙第一7章25〜40節
- 思い煩うことについて、イエス様は何と言われているか書き出してみましょう。
- 主に【奉仕する・εὐπρόσεδρος】とは、どのようなことでしょうか。原語の意味から考えてみましょう。
25、未婚の人たちについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主のあわれみにより信頼を得ている者として、意見を述べます。
26、差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのがよい、と私は思います。
27、あなたが妻と結ばれているなら、解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら、妻を得ようとしてはいけません。
28、しかし、たとえあなたが結婚しても、罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても、罪を犯すわけではありません。ただ、結婚する人たちは、身に苦難を招くでしょう。私はあなたがたを、そのような目にあわせたくないのです。
29、兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは、妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。
30、泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は①所有していないかのようにしていなさい。
31、世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世の有様は過ぎ去るからです。
32、あなたがたが思い煩わないように、と私は願います。独身の男は、どうすれば主に喜ばれるかと、主のことに心を配ります。
33、しかし、結婚した男は、どうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、
34、心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は、身も心も聖なるものになろうとして、主のことに心を配りますが、結婚した女は、どうすれば夫に喜ばれるかと、世のことに心を配ります。
35、私がこう言うのは、あなたがた自身の益のためです。あなたがたを束縛しようとしているのではありません。むしろ、あなたがたが品位ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようになるためです。
36、ある人が、自分の婚約者に対して品位を欠いたふるまいをしていると思ったら、また、その婚約者が婚期を過ぎようとしていて、結婚すべきだと思うなら、望んでいるとおりにしなさい。罪を犯すわけではありません。二人は結婚しなさい。
37、しかし、心のうちに固く決意し、強いられてではなく、自分の思いを制して、婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、それは立派なふるまいです。
38、ですから、婚約者と結婚する人は良いことをしており、結婚しない人はもっと良いことをしているのです。
39、妻は、夫が生きている間は夫に縛られています。しかし、夫が死んだら、自分が願う人と結婚する自由があります。ただし、主にある結婚に限ります。
40、しかし、そのままにしていられるなら、そのほうがもっと幸いです。これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思います。
はじめに—
こちらのバラは、以前お話ししました、枯れてしまったと思い諦めて、鉢の土がカラカラに渇いているのが視界の隅に入っても見て見ぬ振りをして、水やりもせずに放っておいた木が、実は根っこは生きていて、まだ実際には寒いけれども、季節は確実に進んでおり、春が近づいていることを知っているそのバラの木が芽を膨らませてきたことに驚き、そして霊的に励まされたという、そのバラがついに今朝咲かせた花です。改めて励まされます。たとえ人が枯れて死んだように見えても、すべてをご存知の神はその人の内にあるいのちを認め、決して見放すことなく御霊を注ぎ続けられるのです。御霊、聖霊のことを聖書は「生ける水」とも言います。また御霊、聖霊は父なる神の霊、心、つまり親心です。子を思う親の心。私たちも植物が大好きな方であればなおさら、水をやる時にただ水を心なくぶっかけるのではなく、そこに植物に対する愛情が込められているのではないでしょうか。ごめんねとか、元気になってねとか、きれいな花を咲かせて私を喜ばせてねとか。神もそのような思いとともに生ける水を人に注ぎ続けるのではないでしょうか。父なる神は、いろいろな出来事によって死んでしまっているような私たちを、決して諦めない愛とあわれみによって見つめ続けられ、御霊を注ぎ続けられ、そしてきれいな花を咲かせ、さらには豊かな実を結ぶことを、あわれみながら(時には断腸の思いで)心待ちに待っておられるのです。私も今朝、思わず「頑張ったね」とバラに話しかけてしまった、気持ち悪いおじさんになっていることに気づいて、思わず自分で笑ってしまいました。しかし天の父なる神に「頑張ったね」などと語りかけられたら、やはりとても嬉しいですね。
さて、本朝もコリント人への手紙第一の講解を進めてまいります。
私たちの目はどこを向いているだろうか
私たちの目はどこを向いているでしょうか。
イエス様は言われました。「目はからだのあかりです」(マタ622)と。そのように言われるのは、目は「窓」のようなもので、その目を通して光が体、あるいや霊、心に入ってくるからです。そしてその目がからだのあかりとして良い効果を発揮するのは、「健全であるかどうか」にかかっています。「健全である」というギリシャ語には他に「単一の」という意味があり、それは分割されていないということです。分割されていない単一の目、一点に焦点を合わせた目を持つならば、目は私たちに行くべき道を体や心に示すことができます。そして私たちはそこに向かって全身全霊で進んで行くことができるでしょう。
では、私たちが焦点を合わせるべきものは何であるか。聖書は何と言っているでしょうか。聖書の最後はヨハネの黙示録ですが、そこには何が記されているでしょう。それは再臨のイエス・キリストであり、イエス・キリストを通して完成される天の御国、神の国に、イエス・キリストを通して私たちが入れられることです。そしてイエス・キリストとともに神の国を受け継ぐことです。
主は「目はからだのあかりです」と教えられた後、私たちの目がどのような状態か、またどのような方向に向いているか反省してみるように問いかけられました。そして言われたのです。「だれも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなたがたは神と富とに仕えることはできません」(マタ622-24)と。
前回は「召された状態にとどまり、“自分から無理に”環境や境遇を変えようとするのではなく、すべての人に分け与えられている神の賜物を用いて、そこで良い実を結ぶように」と教えられました。そして今日の箇所でパウロは言います。「召された状態にとどまって、信仰の戦いに備えるべきである」ことが教えられます。「備える」というのは、ある事態が起こった時にうろたえないように、また、これから先に起こる事態に対応できるように準備しておくということです。ある事態とは何でしょうか。パウロは29節で「時は短くなっています」と言います。26節では「差し迫っている危機のゆえに」と言います。パウロの視線は明らかに「終わりの時、終末」を見ています。
そして今日の箇所では主に結婚に対する教えが語られますが、これらは現在の、当時とは異なる歴史的、社会的、民族や文化的背景では適用することが難しい部分もありますが、しかしこの教えの基礎となっているのが、パウロの終末に対する認識と理解であることを見落としてはなりません。もしかしたら教会も、未来に完成される神の国を見つめさせることよりも、現在を生きることに関してばかり語りがちなのかもしれません。今日の箇所で私たちは、終末の時代、終わりの時を生きる現代の私たちにも有効である、神の国の完成へと向かうために必要なメッセージを受け取らせていただきたいと願います。
今、私たちは確実に終わりの時を生きている
パウロはこの手紙をエペソの町で書きました。そのエペソの町で彼は迫害に遭いました。そのことを15章では「獣と戦った」(1532)と言っています。黙示録では終わりの時の「獣」との戦いが記されています。つまりパウロは終わりの時、差し迫っている危機をひしひしと感じていたのです。
7章26節 差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのがよい、と私は思います。
最近の箇所で何度も「よい」と出てきますが、これは「必要である」とか「道徳的にまさっている」という意味ではなく、「おすすめできますよ」「〜よりもこっちの方が良いですよ」という意味の語です。なぜそのように勧めるのかというと、パウロは「あなたがたを、そのような目にあわせたくない」と思っているからです。「そのような目」とは、その身に苦難を招くこと、身に苦労を負うことになるということです。
未婚の男性はそのままの状態にとどまっているのがお勧め。その理由は、今は危機が差し迫っている時であるからです。この危機が差し迫っている今、結婚している男性は離婚しようとしてはいけないと言います。当時は料理が焦げたという理由でも妻を追い出すことができました。妻が気に入らないからと言って、簡単に離婚できてしまいました。そのような行いは、神の愛、あわれみ、恵みを強調するキリストの教会には似つかわしくないものでした。神の一方的な愛、あわれみ、赦し、すべて恵みによって救われた者がそのようなことをするのは、どう考えてもおかしなことです。周囲の人々にも神の愛、あわれみ、恵みを証することなどできません。また、離婚するために一生懸命になるならば、目が単一ではなくなってしまう。分散されてしまう。神から離れてしまうことになります。それはとても危険なことなのです。もしそのような時に、主が盗人のように再び来られたらどうなるでしょうか。そのことは未婚の男性にも同じことが言えます。妻を得ようとしてはいけない。別訳では「妻を求めてはいけません」となっています。終わりの時の今、神以外の何かを求めて、そちらばかりに心が向いて、主を忘れてしまっては危ないのです。身に苦難を招くことになります。この苦難というギリシャ語は、「迫害、苦悩、煩わしく苛立たしい出来事、さらには壊滅的な出来事」という意味の語です。壊滅的な出来事。それは「永遠の死」のことでしょう。この世での死ではありません。死の先にある永遠のいのちを死んだように生きるということでしょう。
ちなみに、私は卒論で死後のことを扱ったのですが、その学びの中で知ったことは、イエス様が死後の世界のたとえの中で使われる「苦しみ」というギリシャ語は、すべて精神的な苦しみを表す語が使われているということです。聖書に地獄という言葉はありませんが、もし死後、そのような所に行って永遠に精神的な苦しみを味わいながら生きて行かなければならないなど、考えただけで恐ろしいと思いませんか。神学校からの帰り道の車の中でそんなことを思い巡らしながら信号待ちをしていた時、思わず車の窓を開けて隣の車の人に「今すぐイエス様を信じてください!」と言いたくなりました。皆さんも大切な人が永遠に精神的な苦しみを味わいながら生きて行かなければならいなどという、そのような悲惨な目に遭わせたくないと思われるなら、今すぐにイエス様を伝えてあげてください。しかしなかなか言葉で伝えることは難しいと感じてしまいます。言葉で伝えることができないなら、私たちの生き様で伝えるしかありません。話しは逸れてしまいましたが、とにかく神は人が永遠にそのような悲惨を生きることなど1ミリも望んでおられないのです。それでイエス・キリストをこの世にお送りくださったのです。
もちろん、結婚することは罪ではありません。結婚は神が定められた祝福です。主にある結婚であるならば、それはかえって神の祝福となります。それが主にある者同士の結婚であるならば、さらなる祝福となり、ともに励まし合い、慰め合い、教え合い、信仰ゆえのこの世での苦難に立ち向かうことができます。しかしパウロは、未信者との結婚から生じる様々な危険や困難などを心配し、それならばこっちの方が良いですよと、独身の方を勧めるのです。「時は短くなっています」、「差し迫っている危機のゆえに」。パウロの視線は明らかに「終わりの時、終末」と言われる今を見ているのです。
この世の事柄を過大に重視してはならない
パウロは結婚を取り上げていますが、それ以外にもこの世の事柄、それこそ富(お金、家、車など)、あるいは自分の願望や欲望などを【必要以上に】重視することのないように、この世の歴史はすでに終末を指して急いでいる、時は縮まっているということを指摘します。
7章29節 兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは、妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。
7章30節 泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。
7章31節 世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世の有様は過ぎ去るからです。
「時は短くなっています」。このギリシャ語は「引き寄せられている、締めくくられる、終わらせる、完成される」を意味しています。まさにこの世の歴史はすでに終末を指して急いでいるということです。
今からは、妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。これは独身のように自分を扱って、自由気ままに楽しく暮らしなさいということでしょうか。分別のある皆さんであるならすでにお分かりだと思いますが、33節にあるとおり、「結婚した男は、どうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、そちらの方に心を分かれさせ、目も体も心もすべて持って行かれてはならない」ということです。泣いている人は泣いていないかのように。喜んでいる人は喜んでいないかのように。これもギリシャ語の意味からあたってみたいのですが、「泣く」というギリシャ語の意味は「泣く、嘆く、悲しむ、塞ぎ込む」です。そして「喜ぶ」というのは「喜びが大きい、満ち足りている」です。それはその後の「買う人は所有していないかのようにしていなさい」にも通じるものがあるでしょう。所有している人は所有していないかのように。持っているものに満ち足りたり固執したりしていてはならないということでしょう。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。関わっても良いし、世に関心を持って世に奉仕し貢献することは主の御心にかなっていることだと思いますが、やはり神からそれぞれに分け与えられた賜物の分を超えて、人間の知恵によって過度に関わりすぎてはならないのです。この世の有様は過ぎ去るからです。また、この世の形、習慣、慣習、流行り、そういったものに関わりすぎてはならない。それらは間もなく過ぎ去る、死ぬ、再び戻ることはない、完全に消失するからです。
7章32節 あなたがたが思い煩わないように、と私は願います。
何も思い煩わないで。この「思い煩う」について、主イエス様のみことばに聞きましょう。
「茨の中に蒔かれたものとは、みことばを聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑がみことばをふさぐため、身を結ばない人のことです」(マタ1322)。
「この世の思い煩いや、富の惑わし、そのほかいろいろな欲望が入り込んでみことばをふさぐので、実を結ぶことができません」(マコ419)。
「彼らはみことばを聞いたのですが、時がたつにつれ、生活における思い煩いや、富や、快楽でふさがれて、実が熟すまでになりません」(ルカ814)。
「主は答えられた。『マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って、心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです』」(ルカ1041-42)。
「あなたがたの心が、放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように、突然あなたがたに臨むことにならないように、よく気をつけなさい」(ルカ2134)。
「あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配してくださるからです」(Ⅰペテ57)。
今日の箇所の32節と33節には「心を配る」とあり、34節には「心が分かれる」とあります。思い煩う、心配するというのは、不安になり、気にかけて、色々なところに関心が向いて、色々なところに心を配り、心が分かれてしまうことです。そしてイエス様が言われたとおり、人は不器用で知恵も力もなく弱いもので「二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなたがたは神と富とに仕えることはできない」のです。私たちの目はどこに向いていて、私たちの心はどこにあるでしょうか。誰に仕えているでしょうか。終末を指して時は急いでいる今、私たちは改めて顧みる必要があります。
パウロがこう言うのは、あなたがた自身の益のため
7章35節 私がこう言うのは、あなたがた自身の益のためです。あなたがたを束縛しようとしているのではありません。むしろ、あなたがたが品位ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようになるためです。
パウロはなかなか厳しいこと、中には理解しがたいことを言いますが、これらは読者自身の益のため、恩恵を受けるためです。束縛しようとしているのではないとパウロ自身も言っています。この「束縛する」というギリシャ語も興味深いもので、ロープやコードで輪を作り、一端を引くと輪が締まる結び方。具体的には、投げ縄や首吊り縄などに使われる「輪縄」を指す語です。パウロは「あなたを奴隷として連れて行くものでも、あなたを絞め殺すためのものではなく、あなたを真に生かすものである」として勧めるのです。だったらこっちの方が良いですよと。
今日はギリシャ語の勉強のようになってしまいますが、「奉仕」というギリシャ語もとても興味深い語ですので、ぜひご一緒に学びたいと思います。このギリシャ語の意味は、「常に注意を払い献身的に、忠誠な、熱心な、熱愛する、専念する」という語です。さらに意味があります。それは何と「神に献げられた、のろわれた」という意味。この神に献げられたもの、のろわれたものというのは、つまり「神へのいけにえ」屠られた動物です。そして「木にかけられた者は神にのろわれた者である」(申2123、ガラ313)とも言われていますが、それは十字架の死です。自分を十字架にかけ、自分に死ぬことです。神への奉仕、神を熱愛し、忠誠をもって真心から神に近付き献げられるもの、それは礼拝です。礼拝とは、自分の思いを捨て、つまり自分に死に、神のみことば、御心に聞き従う、それが礼拝です。神への奉仕です。
パウロは言います。「あなたがたを束縛しようとしているのではありません。奴隷として連れて行くのでも、絞め殺すのでもない。むしろ、あなたがたが品位ある生活、世の人々の間で認められ、良い影響力を持つような生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようになるため、神を愛し、自分に死に、神のみことば、御心に聞き従うようになるためです」と。神のことばとは何でしょう。神のことばが人となられたイエス・キリストです。神の御心とは何でしょう。「神は、すべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます」(Ⅰテモ24)。
また、「品位」とは、上品さや気高さといった意味を持つ語ですが、人や物事の外面的な印象、つまり外見や行動、言動から感じられる上品さや気高さです。そしてキリスト者にとって品位ある生活というのは、やはり「神を愛し、隣人を愛する」生活でしょう。自分を愛するのではなく、神を愛し、隣人を愛する。つまり自分に死ぬこと。そのような生き様でしょう。
36節から38節に述べられていることは、つまりはこのことなのだと思います。結婚するのも、結婚しないのも、婚約者である相手を真実に愛することによる決断。誰からも強いられてでもなく、自分の思いを制して、自分の欲望を後回しにし、自分に死に、結婚しよう、または婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意する。真実の愛によって、相手の本当の益のために、つまり相手が主に仕えることに専念できるようにしてあげよう、主に仕えることに専念することによって、終わりの日に壊滅的な目に遭うことがないようにしてあげようという、相手の救いのための決意と行動。それはそのまま神を愛することにもなる。主にある品位あるふるまいというのは、そういうことなのであり、そういうものであるべきなのです。
自分に死ぬ辛さは神がすべてご存知である
それにしても、品位ある生活を送り、ひたすら主に奉仕する生活。ひたすら自分を主に献げ、自分に死に、自分を殺し、主のみことば、御心にとことん従って行くというこの世における人生。それは時に辛いものです。苦しいものです。私たちにとって束縛、主による辛い束縛、主に絞め殺されるような経験となるかもしれません。しかしパウロは「あなたがた自身の益のためである」と言い切ります。
話しは変わりますが、私は民数記22章に出て来る、ろばが話し出す場面がとても好きです。バラムという人を乗せたろばが、バラムが進もうとする道からそれてしまったので、元の道に戻そうと打つのです。それでもろばは元の道に戻ろうとせずに、両側に石垣のある狭い道に進み、バラムの足を石垣に押しつけたので、バラムはさらにろばを打ちました。さらに進んで行き、狭くて右にも左にもよける余地のない場所に行くと、ろばはバラムを乗せたまま、うずくまってしまいました。バラムは怒りを燃やし、杖でろばを打ちました。すると、主がろばの口を開かれたので、ろばはバラムに言ったのです。「私は、あなたが今日この日までずっと乗ってこられた、あなたのろばではありませんか。私がかつて、あなたにこのようなことをしたことがあったでしょうか。」バラムは答えた。「いや、なかった。」そのとき、主がバラムの目の覆いを除かれました。するとバラムは、主の使いが道にはだかり、抜き身の剣を手に持っているのを見ました。バラムはひざまずき、伏し拝みました。主の使いはバラムに言いました。「何のために、あなたは自分のろばを三度も打ったのか。わたしが敵対者として出て来ていたのだ。あなたがわたしの道を踏み外していたからだ。ろばはわたしを見て、三度もわたしから身を避けた。もし、ろばがわたしから身を避けていなかったなら、わたしは今すでに、あなたを殺して、ろばを生かしていたことだろう」(民2221-33)。
もしあの時、ああしていたら、今ごろどうなっていただろう。そう思われたことが皆さんにも何度もあったことと思います。私にもあります。なぜか自分が行こうとする道が何度も閉ざされ、その時はがっかりし、落ち込み、悲しくて、「主よ、なぜですか」と文句を言ってしまった。けれども今になってみると、それが主の最善であったことを知るのです。あぁ良かった、命拾いをしたと思うのです。苦しみにある時は本当に辛いのです。苦しいのです。死んだようになります。周りの人たちも落ち込む私を見て、私が死んだかのように見えたかもしれません。しかし主は決して私を忘れてはおられませんでした。見放してはおられませんでした。かえって最善を用意して、決して諦めない愛とあわれみをもって見つめ続けておられ、御霊を注ぎ続け、親心を注ぎつづけ、「ごめんね、元気をだしなさい、良い実を結びなさい」と、私が必ず良い実を結ぶために断腸の思いをもって導いてくださっていた。
7章40節 しかし、そのままにしていられるなら、そのほうがもっと幸いです。これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思います。
前々回、パウロは結婚しており、彼が復活のキリストと出会い、回心しクリスチャンになった時に妻に去られたのではないかという、賛否両論を生んだ意見を申し上げましたが、この40節を見ると、やはりそうだったのではないかという思いがこみ上げてくるのです。パウロは偉そうに「神の御霊をいただいている、神の代弁者である私の意見だ」と言っているのではなく、彼の本当に辛くて苦しい経験、自分に死ぬという経験を通して、そこから「私も神の御霊をいただいていると思います」と言っているのだと思います。この私パウロは、だったらこっちの方が良い、〜をお勧めしますと、そう述べているのでしょう。
私たちは、私たちの罪の為に十字架で死に、そしてよみがえり、私たちの救いの完成のために再び世に来られるイエス・キリストを信じ、イエス・キリストの再臨によって完成される神の国を、本当に待ち望んでいるでしょうか。目の前のことだけに関心があって、目の前のことだけに一生懸命なのではないでしょうか。本当に見つめるべきものを見つめ、そしてそれを目指しているでしょうか。パウロはこの世のすべてのものやことを諦めろとか、どうでも良いとか、そのようなことは言っていません。私たちはこの世にあって、この世に関するものであらゆるものを神に求めても良いのです。しかし「何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、私たちの願い事を神に知っていただく」(ピリ46)のです。思い煩うことについては、つい先ほどイエス様のみことばに聞きました。ぜひ何度も思い巡らせ、覚えてください。
もし、望みを失い、何が望みなのか分からなくなり、迷ったり、悲しくなったり、苦しくなったりしたならば、何よりも求めるべきものがあること、何よりも求めることができるものがあることを思い起こしましょう。神の国にはそれだけの価値があるのだということを思い起こしましょう。この世の何かに心奪われ、霊的にガッチリ一心同体となってしまうなら、それが引き剥がされる時にどれほどの痛みや苦しみがあることでしょう。だったら、神の国に心奪われ、霊的にガッチリ一心同体となっていた方が断然良い、そっちの方がおすすめできます。
今は終わりの時。終末はイエス・キリストの到来、十字架の死、贖い、復活によってすでに始まっており、後の完成を待つ時です。それは今です。その今を私たちは生きています。私たちはキリストの再臨までに自分たちに与えられた賜物を最大限活用することに関心を傾けて、それに集中するものでありたいと願います。神を愛し、隣人を愛し、品位ある生活を送り、神が喜ばれることを考え、そしてもっと多くの人が主に立ち返るように、福音と信仰を世の人々に、この身をもって伝えることに重点を置く。それがパウロの望みでした。そのために、それぞれ召されたままに神とともに生活することを勧めたのです。神の国の完成へと向かう聖徒へのパウロの一貫したメッセージ。終末の時代を生きる現代の教会と聖徒にも有効なメッセージを覚え、私たちは救いの完成である神の国を一心に見つめ、そこを目指して主に仕えてまいりましょう。奉仕してまいりましょう。さきほどの「奉仕」の言葉の意味を、どうぞ振り返っていただき、こちらも思い巡らせていただきたいと思います。