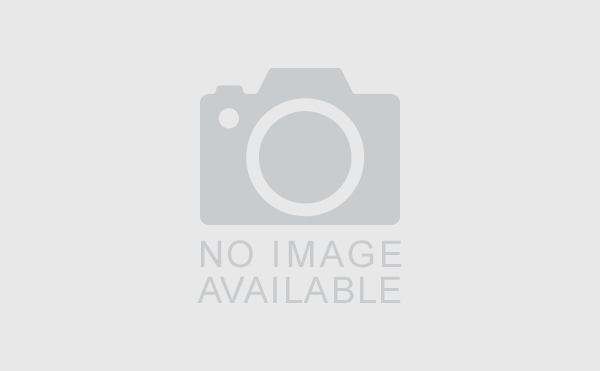2025年1月5日 主日礼拝「教会が与えられている恵み」
礼拝式順序
賛 美 新聖歌481「祈ってごらん」
新聖歌420「雨を降り注ぎ」
前奏(黙祷)
招 詞 詩篇100篇1〜5節
讃 美 讃美歌1「かみのちからを」
罪の告白・赦しの宣言
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 讃美歌411「すべしらす神よ」
聖書朗読 歴代誌第二6章18〜21節
説 教 「教会が与えられている恵み」
讃 美 讃美歌196「うるわしきは」
聖餐式 信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
讃 美 讃美歌205「わが主よ、今ここにて」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 歴代誌第二7章15〜16節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
歴代誌第二6章18〜21節
説教題
「教会が与えられている恵み」
今週の聖句
「今、わたしはこの場所でささげられる祈りに目を開き、耳を傾ける。今、わたしはこの宮を選んで聖別した。それはとこしえにわたしの名をそこに置くためである。わたしの目とわたしの心は、いつもそこにある」
歴代誌第二7章15〜16節
説教「教会が与えられている恵み」
歴代誌第二6章18〜21節
2025年元旦礼拝に続いて、本年最初の主の日の礼拝となります。改めてこれまでの主の守りと導きに感謝するとともに、この1年も、主によってここ長野聖書教会に集められているお一人ひとり歩みが、そして長野聖書教会としての歩みが、主によって守られ、主のご栄光のために用いられますよう期待し祈るものです。
これまでの主の守りと導きを覚えつつ、改めて過ぐる1年を振り返ってみてどうでしょうか。私たちには一瞬でも主を忘れてしまった時がありました。主にあまり注意を向けずにいい加減にしてしまっていた時がありました。困難な中、忙しさの中、不安の中、悲しみの中、悔しさの中、あるいは人間的な享楽に目も心も奪われ、主を見失い、主から離れてしまっていた時もあったでしょう。しかし私たちがそのような時であっても、主は決して私たちを忘れてはおらず、御目を注いでくださり、特別に顧みてくださっていたことを覚えます。私たちの祈りに耳を傾けてくださり、私たちが祈れない、祈らない時でさえ、聖霊なる神が私たちとともにいて、私たちの本当の必要を執り成し祈ってくださっていました。そしてその祈りに答え、私たちが本当に必要としているものを恵みによって与えてくださいました。私たちは決してひとりではなかった。振り返ってみると、それらが分かるのではないでしょうか。そして主は、そのような私たちに教会を与え、互いに執り成し祈る兄弟姉妹を与えてくださいました。神が弱い私たちには必要であるとし、神が神の知恵と恵みによって与えてくださっているのです。
私は朝の仕事に出かける前に教会に寄り、講壇に向かって立ち、使徒信条を告白し、主の祈りを祈ることを日課としています。していました。今は寒くなり「ずく」がなくなってしまい、私の弱いところなのですが・・・。ある人には、それは異教的な行いのように思われ、笑われるかもしれません。しかし朝の静けさの中、教会でそのようにする時に、感覚としては家で祈るのとは全然違う、私個人の信仰告白や祈りではなく、教会としての信仰告白、そして祈りへと導かれるのです。その時、ああ、主はこの教会を愛し、ここに御目を注いでくださっており、ここで献げられる信仰告白、そして祈りを求めておられ、そしてそれを喜んで聞いてくださっているのだということ、また教会を通して一人一人を祝福してくださろうとしているのだということを、ひしひしと感じるのです。
ソロモンの神殿奉献の祈り
本朝与えられましたみことばは、Ⅱ歴代誌6章18〜21節です。
Ⅱ歴代誌6章は、ソロモンが神殿を建設し、その神殿を神にお献げする神殿奉献式の中での「神殿奉献の祈り」となります。そしてここは現代でも主の宮、神の宮とされる教会堂落成の際、献堂式の式辞や祈りに引用されるところですが、確かにそれにふさわしい内容を持つところだと思わされます。「宮」というのは、「住む所」です。主の宮、神の宮、教会は、実に主が住まわれる所。新年最初の主の日の礼拝にあたり、私たちは改めて私たちに教会が与えられているという恵みを知る者とされたいと願います。
神殿の完成には実に7年を要しました。ついに工事は終わり、いよいよ神の箱を神殿に運び入れる時が来ました。そして神の箱が神殿に運び入れられ、定められた場所「至聖所」に置かれ、祭司たちが聖所から出て来ると、列席したすべての祭司たちがまるで一人のように一致して主を賛美し、ほめたたえました。
5章13節 ラッパを吹き鳴らす者たち、歌い手たちが、まるで一人のように一致して歌声を響かせ、主を賛美し、ほめたたえた。そして、ラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声をあげ、「主はまことにいつくしみ深い。その恵みはとこしえまで」と主に向かって賛美した。そのとき、雲がその宮、すなわち主の宮に満ちた。
5章14節 祭司たちは、その雲のために、立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。
主の宮という建物の目的
その荘厳な光景を目の当たりにし、ソロモンは確信して言いました。
6章1節 そのとき、ソロモンは言った。「主は、黒雲の中に住む、と言われました。
6章2節 そこでこの私は、あなたの御住まいである家を建てました。御座がとこしえに据えられる場所を。」
主の宮に雲が満ちたという描写は、主の宮という建物の目的を明らかにします。そこが神が住まわれる、神が臨在される場所だということです。また、主の宮に雲が満ちたということは、その場所を神がそこに住まわれるということを承認されたということでもあります。主の宮に雲が満ちた、その光景を目の当たりにしたソロモンは確信したのです。「確かにここは、主が住まわれる所、主の宮。御座がとこしえに据えられる場所である」と。
私たちに与えられている長野聖書教会に、雲が満ちたという荘厳な光景をご覧になったことがあるでしょうか。もう身動きもできないほどに雲に覆われたなんてことはあるでしょうか。あるのです。「祭司たちは、その雲のために、立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである」。雲が満ちたというのは、主の栄光が満ちたということです。「栄光」というヘブル語のもともとの意味は「非常に重いもの」です。重量感たっぷり。押しつぶされそうなほどのもの。そしてソロモンはこの雲を「黒雲」と言っています。黒雲というのは、闇で覆う雲のことではなく、雨を降らせる黒い雲のことです。雨露をしたたらすところから、恵みと結びつく意味を持っています。以前、ブラジルから来られた方と「御利益」という日本語をポルトガル語で何と言うのか電子辞書で調べたところ、「雲」と出て来ました。御利益というのは神が人間に与えるお恵みのことです。それが雲である。その時はピンと来なかったのですが、そのブラジルから来られた方は「ああ、なるほどね」と、すごく納得していました。
黒雲、雨を降らせる黒い雲。そしてそれが神の栄光である。主の栄光が神の宮に満ちるというのは、つまり神の恵みが神の宮に満ちるということです。長野聖書教会も、神の恵みが満ちあふれています。ある方にここに教会を建てたいという志が与えられたのも、そのための必要が与えられて実際に教会が建てられたことも、今日まで教会が守られて来たことも、救われる魂が起こされてきたことも、信仰の継承がなされてきたことも、一人また一人とこの群れに加えられてきたことも、またこの教会から天に送ることができたのも、外壁の修繕がなされたことも、すべて神の恵みです。私たち一人一人がここに呼び集められたことも、毎週ここで礼拝が守られていることも、神のみことばが語られ、神のみことばが宣言され、主を賛美できるのも、すべて神の恵みです。恵みに満ちあふれている、神の栄光に満ちあふれているではありませんか。私たちの霊的な目を開いていただくならば、かの人が天の軍勢がぐるり取り囲んでいるのが見えたように、神の恵み、栄光が私たちを取り囲んでいる。それを見る時、私たちには身動きができないほどの感謝、感動が湧き起こってくるのではないでしょうか。同時に人間の、いや自分の小ささ、無力さをも痛感させられるのではないでしょうか。しかし、神の栄光が神の宮を神の宮とするのです。神の恵みが神の宮を神の宮にしたのです。神の栄光、神の恵みが長野聖書教会を神の宮とした、しているのです。ですからここは確かに神の宮、神が住まわれる所なのです。
6章18節 それにしても、神は、はたして人間とともに地の上に住まわれるでしょうか。実に、天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮など、なおさらのことです。
ソロモンは主の宮に雲が満ちた、その光景を目の当たりにして確信しました。「確かにここは、主が住まわれる所、主の宮。御座がとこしえに据えられる場所である」と。しかし同時に、天地を創造された偉大な神が、そこに収容されることなどあり得ないことも知っていました。預言者が言っているとおり、いと高き方は、人間が手で作った家にはお住みにならないということを知っていました。また、人間が容易に、軽率に近付くことなどできない神であることも知っていました。そのことを知った上で、人が神に近付き、礼拝することが出来るように神殿を建てたのだと言うのです。なぜでしょうか。
それは、神の宮の意義、神の宮が存在する価値を、このように求めていたからです。
祈りの家
6章19節 あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神、主よ。あなたのしもべが御前にささげる叫びと祈りを聞いてください。
6章20節 そして、この宮、すなわち、あなたの御名をそこに置くと言われたこの場所に、昼も夜も御目を開き、あなたのしもべがこの場所に向かってささげる祈りを聞いてください。
「名をそこに置く」と言われていることは、神がみこころによってご自分の臨在をそこに置かれるということです。宮が文字どおり神の宮であり得るのは、主があえてそこに臨在してくださるからです。神の宮、教会は「天も、天の天も…お入れすることができ」ないお方が、あえて人々とかかわってくださるための神殿なのであり、単なる象徴やしるしではないのです。
そして、主の宮、教会は「祈りの家」であるということです。イエス様も言われました。「わたしの家は、祈りの家と呼ばれる、呼ばれなければならない」と。ソロモンは、祈りにおいて、神と人が実際に出会う場としての神の宮の存在価値を求めたのです。そして主の宮に雲が満ちました。その場所を神がそのように承認されたのです。認めてくださったのです。主の宮に雲が満ちた、その光景を目の当たりにしたソロモンは確信したのです。「確かにここは、主が住まわれる所、主の宮。御座がとこしえに据えられる場所である」と。神殿建設のわざが、真に神のみこころにかなったことであると確認し、更にすべてが神ご自身から出たことであることを再確認したのです。求めるよりも先に、求められていた、与えられていたのです。主は言われました。「今、わたしはこの場所でささげられる祈りに目を開き、耳を傾ける。今、わたしはこの宮を選んで聖別した。それはとこしえにわたしの名をそこに置くためである。わたしの目とわたしの心は、いつもそこにある」(Ⅱ歴715-16)。そして「あなたがたの声は聞き届けられ、あなたがたの祈りは、主の聖なる御住まいである天に届く」と。
主の宮には、そこに向かって主の目が常に開かれている。教会は主の注目の的。常に関心をもって見守っておられる所。そしてそこに向かって人がささげる祈りを常に聞いてくださる。祈りがささげられるならば即座に聞き届けてくださるという約束があるのです。慰めがある、励ましがあるのです。私たちが祈りをささげようとするよりも前に、すでに神ご自身が先にここへ来て、今か今かと待ち構えて、祝福しようとしておられるのです。何かを申し上げようという前に、すでに祝福と応答を用意してここで待っていてくださっているのです。何と感謝なことではないでしょうか。恐れさえ覚えるのではないでしょうか。これを知る事によって、いよいよ神への信頼と感謝が増し加わり、私たちの心と身体は主の宮へ、祈りの家へ、教会へと向かうのではないでしょうか。
祈りは私たちにとって、場所に制限されるものではありません。自分の家でも祈れるし、道を歩いていても、小川のほとりでも、人混みの中でも、広い世界のどこにいても、祈れるのです。なぜなら、この新約の時代、一人ひとりに聖霊が注がれ、一人ひとりに聖霊なる神が住まわれ、一人ひとりが神の宮とされているからです。しかし、特別に教会に来て祈る、教会に向かって祈ることの大切さをここに覚えたいのです。異教的でしょうか。偶像的でしょうか。しかし主が約束されているのです。「今、わたしはこの場所でささげられる祈りに目を開き、耳を傾ける。今、わたしはこの宮を選んで聖別した。それはとこしえにわたしの名をそこに置くためである。わたしの目とわたしの心は、いつもそこにある」(Ⅱ歴715-16)。神は教会を取り上げておられません。与えてくださっているのです。保ってくださっているのです。迷いやすい、見失いやすい私たちのために灯台のように教会を与え、ご自身の臨在と栄光で満たしておられるのです。そこに祝福があり、慰めがあるのです。そこであなたがたを待っている。そこで祈りにおいてあなたがたに会おうと約束された主のおことば(約束)があるからです。私たちはこの主の約束を心から信じ、そして感謝し、従う者でありたいと願います。初詣でに全国から善光寺に集まって来る人たちや、イスラム教徒がメッカに向いて祈るとか、それらに私たちは負けてはいられません。彼らの信仰、彼らの忠実さに負けず劣らず、私たちの心は教会に向かって、あるいはまさに教会に来て、様々な邪魔や妨害を必至に乗り越えて教会に来て、そして祈りたいものです。祈るのです。教会へ来なくても、水曜日でなくても、木曜日でなくてもと、それをしないことの弁解はいくらでも考えられます。しかし、理屈抜きに大切なのです。
6章21節 あなたのしもべとあなたの民イスラエルが、この場所に向かってささげる願いを聞いてください。あなたご自身が、あなたの御住まいの場所、天からこれを聞いてください。聞いて、お赦しください。
祈りの家で献げられる祈りの重大さ
21節から続く所では、人生のあらゆる危機に、課題に、教会という場を中心にささげられる祈りの重大さを思わされます。初代教会の人たちは、事ある毎に宮に来て、神に祈り、そして神をほめたたえていました。隣人に罪を犯してしまった時、飢饉や疫病に際して、敵に立ち向かう時、敵に打ち負かされた時、自分に与えられている責任のこと、あの人のこと、この人のこと・・・。人生の危機にいつも、祈りの家である主の宮がここにあることの恵みを覚えさせられます。今の私たちにとっては、教会こそ、その祈りの家なのです。長野聖書教会こそ、主が私たちに恵みによって与えてくださっている祈りの家なのです。その祈りの家である教会に、主は特別に目を注がれ、耳を傾けておられる。教会に向かって、教会に来て、主の親しい臨在を覚える時、そこで思うことはことごとく祈りになるのではないでしょうか。1つの群れとしての祈りとなるのではないでしょうか。自分のことばかりではない、教会のため、教会を通して栄光を現される神のため、兄弟姉妹のための執り成しの祈りとなるのではないでしょうか。イエス様は「わたしの家は祈りの家と呼ばれる」「わたしの家は祈りの家でなければならない。それなのに、おまえたちはそれを『強盗の巣』にしてしまった」と言われました。
ソロモンの祈りから知るもう一つのことは、罪の告白、自らの小ささの意識がはっきりしていることです。主の親しい臨在を覚える時、そこで思うことはことごとく祈りになるのです。主の愛とあわれみ、主の栄光、恵みを前にして、私たちの祈りは感謝と主の赦しを求める祈りとなるのです。主の偉大な愛とあわれみ、主の栄光、たくさんの恵みを前にして、私たちが祈れることと言えば、主にあわれみを求める祈りであって、要求ではありません。主の愛とあわれみ、恵みに十分に応えることができていない、できない自分を悲しむのです。恵みによって罪赦されている自分が、また罪を犯してしまう。そんな自分を嘆き悲しむのです。しかし主は祈るならば聞いてくださるのです。そして祈るならば赦してくださるのです。あなたを赦したい、あなたを祝福したいと、ここで待っておられるのです。祈りとは、自分の小ささや無力さの告白でもあるでしょう。祈れないとか、祈ろうとしないというのは、神への感謝の足りない者、罪の自覚に乏しい者と言わざるを得ません。その人は祈りを必要としないほど満ち足りていて、またよほど立派なのでしょう。「神へのいけにえは砕かれた霊。打たれ砕かれた心。神よあなたはそれを蔑まれません」(詩5117)。神はそのいけにえこそ喜ばれ、受け入れてくださるのです。
さあ、教会へ行こうと私たちが言うときに、私たちにとって教会は何のためなのでしょうか。もちろん、私たちは神を礼拝するためにそこへ行くのです。問われればそれを間違う人はいないでしょう。しかし現実には、私たちはしばしば人間的に過ぎる場合がありはしないでしょうか。友だちに会える、兄弟姉妹に会える、讃美歌が歌えるなどと。あるいは説教を聞くために。どれも重要な要素かもしれません。しかしそれだけで満足していたり、それだけを求めていたりしてはダメなのです。教会へ行こう。私たちは教会へ行く。それはこの宮に注目し、この宮に臨在され、この宮で待っておられると約束してくださっている主と親しく交わるためです。祈りによって直接主と親しく交わるためです。主の臨在のもと、主の栄光、主の恵みを覚え、肌で感じ、心で感じ、そして感謝とともに悔い改めることができる。自分の弱さや無力さ、罪を素直に告白することができる。そこに導かれる。そしてそこに主の栄光が現され、黒雲が満ち、恵みの雨が注がれ、疑いの雲は晴れ、主の豊かな祝福が真っ直ぐに注がれるのです。祝福という語の意味は「神が膝を折られる」でした。つまり神の愛でしょう、あわれみでしょう、赦しでしょう。私たちが何よりも必要としているそれらが豊かに真っ直ぐに、何ものにも邪魔されずに注がれるのです。
そして教会には、同じように兄弟姉妹たちも祈りを捧げているという、連帯の強さみないなものがあります。執り成しの祈りの力が満ちている。天におられる神と、地にいる私たちとの交わりが通じていること。祈りの家という表現は、その意味でいかにも私たちの教会に似つかわしい呼び方ではないでしょうか。
教会ー「神の声によって召し集められた者たち」
今日の箇所に先立って、5章の頭の方をご覧ください。ここでソロモンは、ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上げるために、イスラエルの長老たち、および、イスラエルの部族のかしらたちと一族の長たちをすべてエルサレムに召集しました。そして神殿奉献式にあたり、イスラエルのすべての人々も、王のもとに集められました。ここに「召集された」「集められた」とありますが、このヘブル語の動詞が名詞になると「召し集められた者たち」となり、それが後に新約の時代になると「教会」となります。そしてこのヘブル語の中には「声」という意味合いも含まれています。上よりの声、つまり神のお声がけによってここに召され集められた者たちの群れ。それが教会なのです。確かにこの地上には数え切れないほどの教会があります。しかしその1つ1つが確かに主のお声がけによって一人一人がそこに召され集められた者たちの群れです。そこに確かな主の御心があるのです。
「教会はキリストのからだである」と主は言われます。あなたがたはそのからだの一部分だと主は言われます。主が御心をもって私たち一人一人をこの教会に召され、集められ、それぞれに役割が与えられている。祈りの力の要素とされている。ここで祈るようにと求めておられる。そして「ここで」わたしはあなたを大いに祝福しよう、そして赦そうと言われるのです。「ここで」「ここを通して」経験させられる様々な出来事、主の恵み、祝福を覚えたり、時には人生の危機とも思えるような出来事を通して、主は私たちをともに祈る者とされる。ともに感謝し、そして赦しを求める者とされる。そこに主の栄光、恵み、祝福がある。わたしたちはそのことを覚え、教会生活を守ってまいりたいと思います。この1年、教会に満ちる主の臨在、主の守りと祝福のうちをともに歩んでまいりましょう。主が御声をもって集めてくださったこの教会に向かって、教会に来て祈る。その重要さ、その恵み大きさ、祝福を今、新しい1年の歩みの初めにあたって、改めて覚えさせていただきましょう。