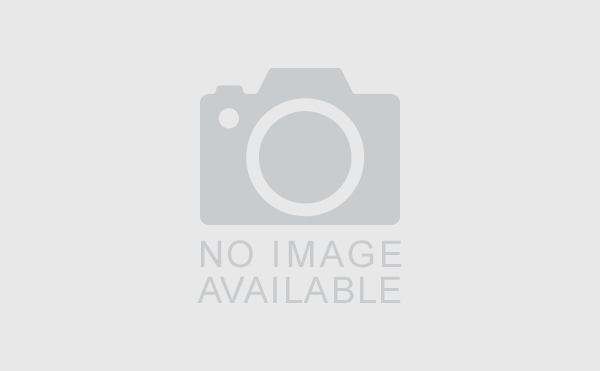2025年4月6日 主日礼拝「主のものとされた幸いな私だから」
礼拝式順序
賛 美
前奏(黙祷)
招 詞 詩篇1篇1〜6節
讃 美 讃美歌16「いときよきみかみよ」
罪の告白・赦しの宣言
主の祈り 讃美歌564「天にまします」
祈 祷
讃 美 讃美歌142「さかえの主イエスの」
聖書朗読 コリント人への手紙第一6章12〜20節
説 教 「主のものとされた幸いな私だから」
讃 美 讃美歌332「主はいのちを」
聖餐式 信仰告白 讃美歌566「使徒信条」
讃 美 讃美歌205「わが主よ、今ここにて」
献 金 讃美歌547「いまささぐる」
感謝祈祷
報 告
今週の聖句 コリント人への手紙第一6章19節
頌 栄 讃美歌541「父、み子、みたまの」
祝 祷
後 奏
本日の聖書箇所
コリント人への手紙第一6章12〜20節
説教題
「主のものとされた幸いな私だから」
今週の聖句
あなたがたは知らないのですか。あなたがたのからだは、あなたがたのうちにおられる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたはもはや自分自身のものではありません。
コリント人への手紙第一6章19節
説教「主のものとされた幸いな私だから」
コリント人への手紙第一6章12〜20節
- 「安価な恵み」「高価な恵み」とは、どのようなものでしょうか。
- パウロはからだについて「消極的命令」と「積極的命令」をしています。それはどのような命令で、どのような理由によるのでしょうか。
はじめに—「安価な恵み」「高価な恵み」
私たちは神の恵みに対して、どのように応えているでしょうか。
ドイツの牧師、神学者であるディートリッヒ・ボンヘッファーの言葉に「安価な恵み」「高価な恵み」というものがあります。「安価な恵み」というのは、彼の言葉を借りるなら「悔い改めのない赦しの説教、教会的訓練のない洗礼、罪の告白のない聖餐、個人としての懺悔のない赦しの宣言」です。これは難しい言葉ではありますが、とても深い言葉です。どうぞ書き留めて、今日ばかりではなく、これからも何度も思い巡らしてみていただくことをお勧めします。主が権威をもって、自由に注いでくださる一方的とも言えるほどの主の素晴らしい恵みを、一方的であるからこそ、その主の恵みに対してそれほどの感動もない、感謝もない、それ故に悔い改めもない、イエス・キリストとみことばへの服従を伴わない。自分勝手に自由に生きる。救われた以前と変わらない生き方。変えられない。変える力(価値)がない。そのような恵みを「安価な恵み」と言います。それに対して「高価な恵み」というのは、これも彼の言葉を借りるなら、「イエス・キリストの招きであり、それに応じて弟子はその網を捨てて、主に従うほどのもの」です。この言葉もまたとても深い言葉です。これも書き留めて、何度も思い巡らせてください。皆さんにとって「恵み」とは何でしょうか。与えられる資格のない者に与えられるもの、与えられたものとは何でしょうか。神の愛ですか。赦しですか。召しですか。イエス・キリストとみことばへの服従へと導く恵み。真の悔い改めがあり、生き方が変わる、変えてしまう力(価値)がある。そのような恵みを「高価な恵み」と言います。
たとえば「安価な恵み」「高価な恵み」を「安価な1万円札、高価な1万円札」としたら分かりやすいでしょうか。同じ1万円札であっても価値が違う。私が17才の頃のドラマで「北の国から’87初恋」というものがあったのですが、そのラストシーンが名場面としてとても有名です(これを聞いてピンと来た方は50代以上の方でしょう)。貧しい父子家庭で育ち、北海道の富良野の中学を卒業して上京する息子の純君。父親の五郎さんは知り合いのトラック運転手に、「息子を東京まで乗せてやって欲しい」と頼みます。出発後、運転手がフロントガラスの前に置かれた封筒をあごで指して「俺は受け取れん」と純君に言います。純君が封筒を開けると、中には泥のついたピン札の1万円札が2枚入っていました。運転手が言います。「おまえの親父の手についていた泥だろう。おまえの宝にしろ。一生とっとけ」。息子を上京させるために一日中必死に働いたお金。手についた泥も洗う暇がないくらい必死に集めたお金。それがピン札であったところもまた、父親の息子に対する愛が伝わってくるようです。それからしばらく経ってからでしょう。1人部屋でその2枚の1万円札を見つめる純君の心の言葉。「そのお札は、いつも体から離しません。何かあると僕はそれを出して見るわけで、そこには今もあの時の父さんの指についていた泥がついており、あの日の日付を忘れないように、僕はこっそり書き入れてあり・・・」。泥だらけの1万円札を見る度に、何を思ったでしょう。申し訳ない、ごめんなさい、ありがとう、お父さんの気持ちに応えて頑張らなくては・・・。純君のその後の生き方を変えるくらいの、それほどの価値をもった1万円札になったはずです。しかし受け取った側の気持ち次第では、同じ1万円札でもその価値はまったく変わってしまいます。親だから当然とか、そこに大変だっただろうなとか、申し訳ないとか、本当にありがとうという感謝の気持ちがなければ、1万円札2枚なんてあっという間にあぶく銭のように消えてなくなってしまうでしょう。頂いたお金は自分のもの。自由に使って良いのです。しかし、大切にするのか、大切にしないのかは、そのお金が誰からもらったものなのか、あるいはそのお金はどのようにして得られたものなのかによって価値が変わってくるのではないでしょうか。そのように、同じ恵みにも安価、高価という違いが生じてしまうのです。当然主の恵みは、本来はとても高価なものであるはずなのです。私たちに天から自由に一方的に注がれる主の恵みには、泥のついた1万円札のように、父なる神の愛、大きな犠牲、御子イエス・キリストの十字架で流された血が伴っているのですから。
さて、本朝もコリント人への手紙第一の講解を進めてまいります。
淫らな行いを正当化する聖徒の試み
今日のところでパウロは、「淫らな行い」というテーマから、「自由」について教えています。
イエス・キリストの十字架の福音。それは神の御子イエス・キリストがすべての罪人の罪の赦しのための神へのいけにえとなられ、罪人の身代わりとなり、一切の罪を背負い、十字架の上で苦しまれ、屠られ、死なれ、そのいのち、流された血潮によって、イエス・キリストを信じる者のすべての罪が赦される。この十字架の福音を信じるならば、あなたの一切の罪を赦そう。罪の奴隷から解放して自由の身としよう。永遠のいのちを与え、神の国、天の御国を相続することができる神の子としよう。このイエス・キリストの十字架の福音を信じ、神が恵みによって与えてくださった、流されたキリストの血による新しい契約を結ばせていただくことにより、ただ恵みによって自由にされ、また幸いな神の子とされたコリントの聖徒たち。ところが彼らの中には、依然として罪に生きようとする人たちが一定数いたようです。そこでパウロは「淫らな行い」を代表例として取り上げ、それをテーマに「自由」について教えます。
1章でコリントの町について見ましたが、コリントは地理的にも富が集中する場所であり、また富があるところではなぜか避けられない、道徳的な不品行の横行で有名な都市でした。町のどこからでも誰もが見上げることができる丘の上には大きなアフロディーテ神殿があり、そこには神殿娼婦がいて姦淫がなされ、神殿男娼がいて男色がなされるなど、あらゆる形の宗教的売春が行われていました。このような不道徳が行われていたコリントに建てられた教会は、これらに抵抗するために努力したことでしょう。しかし中には異なる主張をする人々も一定数いたようです。その一定数の人たちは、「すべてのことが許されている」という主張をして、淫らな行いを正当化しようとしました。「すべてのことが許された。すべてのことが許されている」。しかしそれは規律とか節度なく、勝手気ままに振る舞って良いことを意味するのでしょうか。ほったらかして勝手にさせて良いことを意味するのでしょうか。
間違えてはならないのです。聖徒たちに与えられている自由とは、恵みによって与えられたキリストにある自由なのです。恵みによって十字架のキリストを通して与えられた自由なのです。恵みによって天の父である神の愛と犠牲によって与えられた自由なのです。
その恵み、自由をどのように用いるのか。自由の価値や自由の用い方というのは、この私に与えてくださった方がどのような方であるのか。この私にどのようにして与えられたのか。それに対してこの私はどのように応えるのかによって決まるのではないでしょうか。
6章12節 「すべてのことが私には許されている」と言いますが、すべてが益になるわけではありません。「すべてのことが私には許されている」と言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。
6章13節 「食物は腹のためにあり、腹は食物のためにある」と言いますが、神は、そのどちらも滅ぼされます。からだは淫らな行いのためではなく、主のためにあり、主はからだのためにおられるのです。
6章14節 神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちも、よみがえらせてくださいます。
「すべてのことが私には許されている」「食物は腹のためにあり、腹は食物のためにある」。一部の人たちの間でスローガンのように言われていたのでしょう。あれを食べてはいけない、これを食べてはいけない? あれをしてはいけない、これをしてはいけない? そんなことからは解放されているのだから、私たちは何を食べても、何をしても良いではないか。与えられている自由を喜び楽しみ、自分が望むことは何でもしようではないか! 私たちは許されているのだから! 大声で叫ばないにしても、心に密かにスローガンとして掲げていた人もいたのかもしれません。しかし、パウロは「すべてが益になるわけではない」「私はどんなことにも支配されはしない」と反論します。
「支配されはしない」というギリシャ語は、「制御されない」という意味の語です。すべてが許されてはいても、それが益とならないのならば。すべてが許されていても、自分がそれに支配され、制御されてしまう可能性があるならば。はまってしまい、虜になり、そこから逃れられなくなる可能性があるならば、その自由を(何をしても良いだろうという思いを)行使することを控えるべきであると教えます。なぜならば、イエス・キリストを信じる者は、神のもの、神の子、キリストに属するまことに幸いな者とされているからです。
「からだは淫らな行いのためではなく、主のためにあり、主はからだのためにおられるのです」と、そう言えるのはなぜでしょうか。
私たちのからだは、もはや罪を犯すためのものではなく、主の栄光を現すためのものとされているからです。私たちが神を愛し信じる以上に、神は私たちを愛し信じてくださり、私たちに期待してくださっているのです。このような私に。それを重荷に感じますか、それとも感謝だと思いますか。
「神は主イエス・キリストをよみがえらせましたが、その御力によって私たちも、よみがえらせてくださいます」。神はイエス様を【死の苦しみ(聖書では罪がもたらす肉体的な死とその苦しみのことはもちろんのこと、罪がもたらす霊的な死とその苦しみのことをも言う)】から解き放って、よみがえらせました。この方が死につながれていることなど、あり得なかったからです(使224)。そしてイエス・キリストを信じ、神のもの、神の子、キリストに属する者とされている私たちに対しても「死につながれていることなど、あり得ない!」と言われるのです。
父なる神のみこころは何でしょうか。イエス様がはっきり教えてくださっています。「わたしを遣わされた方のみこころは、わたしに与えてくださったすべての者を、わたしが一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。わたしの父のみこころは、子を見て信じる者がみな永遠のいのちを持ち、わたしがその人を終わりの日によみがえらせることなのです」(ヨハ639-40)。「キリストにあってすべての人が生かされる」(Ⅰコリ1522)。「主イエスをよみがえらせた神が、私たちをもイエス様と“ともに”よみがえらせ、イエス様と“一緒に”神の御前に立たせてくださる」(Ⅱコリ414)。私たちの人生も、私たちの死の先にある永遠の人生も、イエス様抜きには何も始まらないのです。だからイエス・キリストが必要なのです。
今こそ私たちは「すべてのことが私には許されている」「食物は腹のためにあり、腹は食物のためにある」という間違った心のスローガンを書き換え、新しく「(私たちの)からだは淫らな行いのためではなく、主のためにあり、主は(私たちの)からだのためにおられる」というスローガンを掲げようではありませんか!
だれのからだなのか
6章15節 あなたがたは知らないのですか。あなたがたのからだはキリストのからだの一部なのです。それなのに、キリストのからだの一部を取って、遊女のからだの一部とするのですか。そんなことがあってはなりません。
6章16節 それとも、あなたがたは知らないのですか。遊女と交わる者は、彼女と一つのからだになります。「ふたりは一体となる」と言われているからです。
6章17節 しかし、主と交わる者は、主と一つの霊になるのです。
パウロは「あなたがたは知らないのですか」と繰り返します。この手紙を読むコリントの聖徒たちの多くが、キリスト教の知識とか知恵を持っていることを誇っていたことを思い起こしながら、パウロは「あなたがたは知らないのですか」と繰り返すのです。
パウロはコリントの聖徒の淫らな行いを代表とする様々な罪、自分の欲望を正当化して自由に追い求めることが間違いであることの理由について、2つのことを説明します。1つは「あなたがたのからだはキリストのからだの一部だから」。もう1つは「主と交わる者は主と1つとなるように、淫らな行いは遊女と交わって遊女と1つとなる罪だから」。
イエス・キリストをとおして神のものとされた私たちのからだを、私たち自身がどのように使うかが重要なのです。このからだをもって遊女と交わるならば。このからだをもって罪を犯してしまうならば、このからだは遊女のからだの一部になってしまう。「ふたりは一体となる」。罪と一心同体となってしまう。「ふたりは一体となる」というのは、創世記2章24節で神が語られた奥義であり、神の真理です。「ふたりは一体となる」、それはからだばかりでなく、霊も、心も、魂も1つになるということです。引き剥がすことのできない関係、もし引き離そうとするならば、もの凄い痛みと苦しみが伴うもの。それほど強力なもの。姦淫(結婚以外の性的な関係)、罪と結ばれてしまうこととはそのようなものなのです。しかし、主と交わる者は、主と1つの霊になるのです。主の霊、聖霊が注がれ、聖霊が私たちの内に住んでくださっているのです。聖霊が、神の愛が私たちに注がれて離れない。結婚は主と私たちとの関係の型です。主と交わることができる幸い。主と一心同体とされることの幸い。からだも霊も主と1つに結ばれることの幸い。恵みです。「あなたがたは知らないのですか。あなたがたはもはや自分自身のものではありません」。
しかし主から心が離れ、罪の方に心惹かれ、主から引き剥がされる時、やはりそこにはもの凄い痛みと苦しみが伴います。神の真理です。本当のことです。「あなたがたは知らないのですか」とパウロは繰り返し語ることです。神が「そんなことはあり得ない、あってはならない」と言われることです。
からだに対する命令
6章18節 淫らな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて、からだの外のものです。しかし、淫らなことを行う者は、自分のからだに対して罪を犯すのです。
6章19節 あなたがたは知らないのですか。あなたがたのからだは、あなたがたのうちにおられる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたはもはや自分自身のものではありません。
6章20節 あなたがたは、代価を払って買い取られたのです。ですから、自分のからだをもって神の栄光を現しなさい。
パウロは淫らな行い、またそれを代表とする一切の罪に対して、「してはならない」という消極的命令と、「しなさい」という積極的命令を与えます。消極的命令は、「淫らな行いを避けなさい。してはならない」です。罪を克服しなさい、征服しなさいと言うのではなく、避けるべきであると言うのです。逃げるが勝ちです。私たちには罪を征服したり克服したりできる力などないことを知らなければなりません。パウロは別の手紙でこのように言っています。「あなたがたの間では、聖徒にふさわしく、淫らな行いも、どんな汚れも、また貪りも、口にすることさえしてはいけません」(エペ53)。どんな些細なことでも、それを足がかりにして罪は際限なく大きく膨らんで行くのです。パン種のようにです。それに立ち向かうことのできる力ある者はいません。
「淫らな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて、からだの外のものです」とパウロは言います。これもまた聖書が語る真理です。人が犯す罪はすべて、からだの外からのものです。なぜなら、私たちの内に住んでおられる主が「罪を犯せ、罪を犯しても良い」と言うのではないからです。勘違いしてはならないのです。聖いお方はそんなことは言われないのです。「罪を犯しても良い」「これくらいは良い」「こんなことは罪とは言わない」という声は、完全に外からのものです。私たちのからだの外の世界から聞こえる声です。この世の支配者、主から離れさせようとする存在、私たちを騙し、罪を犯させ、最終的に神の前に訴える存在、サタンからのものです。
また、パウロは「あなたがたは知らないのですか。あなたがたのからだは、あなたがたのうちにおられる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたはもはや自分自身のものではありません」と言って、積極的な命令を与えています。3章16節でもパウロは、聖徒のからだは神の宮であり、その中には御霊が住まわれると教えました。そしてここでも同じことを教え、「自分のからだをもって」神の栄光を現すようにと求めます。
そして続けて言います。「あなたがたは、代価を払って買い取られたのです」と。ここではもはや「あなたがたは知らないのですか」とは言いません。なぜなら、このような罪人である私が代価を払って買い取られたことは、十字架のメッセージの中心であり、私たちの救いの中心であり、その恵みを信じて、感謝して、そして悔い改めて、私たちは救われたのですから。神の愛と犠牲を、大変だっただろうなとか、申し訳ないとか、本当にありがとうとか、心から感謝して受け取り、そして救われたのですから。
聖徒が、私たちが自分のからだで罪を犯すのではなく、神の栄光をささげるためには、自分が自分のものではないことをはっきりと認識する必要があります。自分がどのようにして、どのような愛と犠牲によって幸いな神のものとされたのか、自分にはどれほどの価値があるのかをはっきりと認識する必要があります。「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」(イザ434)と仰ってくださる神の声を、神の思いを軽く聞いて、軽く扱ってはならないのです。神の恵みを、安価なものとしてはならないのです。愛される資格のないこの私が愛された。赦されるはずのないこの私が赦されている。神の自由によって、一方的に注がれる主の恵みを、まことに重く価値のあるものとして受け取らなくてはなりません。
私たちにもある「すべてのことが許されているから」という思い
コリントの聖徒は、すべてのことが許されているという主張で、淫らな行いを正当化しようとしました。私たちのうちにも、すべてのことが許されているからという主張で、罪を正当化しようとする試みがあるのではないでしょうか。しかし、私たちに与えられている自由というのは、罪を犯さなくても良いという自由です。自分のからだを罪のために用いなくても良いのだという自由です。自分のからだをもって神の栄光を現すことができるという自由です。
自分のからだをどのように使うかによって、神の栄光を現すことも、神の怒りの対象になることもできます。今、私たちはみことばに導かれ、みことばに従い、自分のからだは誰のものか。どのようなものとされているのか、改めて顧みて、しっかり覚える必要があります。同じピン札の1万円札であっても、泥のついた1万円札にはより価値があるように、私たちのからだも、同じからだであってもそれ以上のかちがあること、またその価値はどのようにしてつけられたのかを覚える必要があります。
前回のところでもパウロは言っていました。「あなたがたは知らないのですか。正しくない者は神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。淫らな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒におぼれる者、そしる者、奪い取る者はみな、神の国を相続することができません。あなたがたのうちのある人たちは、以前はそのような者でした。しかし、主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によって、あなたがたは洗われ、聖なる者とされ、義と認められたのです」(69-10)。パウロは「あなたがたは知らないのですか」と繰り返すのです。手紙の読者が多くのキリスト教知識と知恵を持っていることを誇っていたことを思い起こしながら、パウロが繰り返して言っていることに、私たちも注意しなければなりません。
私たちにも罪があります。捨てきれない、拭いきれない罪があります。それを主の助けをいただいて捨て去りましょう。今朝の招きのことばの詩篇1篇にある「風が吹き飛ばす籾殻」のように、欲望のままに、欲望を追求して自由に飛び回って生きられることが本当の幸せではないこと。主にとどまり、主のみことばに留まることができる自由。罪を犯さなくても良い自由。私たちのこのからだをもって、主の栄光を現して行くことができる自由。そのような生き方こそ、本当の幸せなのだということを覚えたいものです。主の恵みに心から感謝して、詩篇1篇の「なんて幸せなんだろう!」という詩篇の記者の叫びを、私たちも叫びたいものです。